この記事では、2024年11月08日に行われる株式会社ライセンスアカデミーのイベントにおける基調講演講師をお引き受けした経緯についてまとめます。講演の中に収まらないエピソードなどを執筆しました。
Webセミナーを受けていたら、ある日突然発表者を初体験
X(旧Twitter)でつながった村上先生主催の「#zoomでハナキン」というオンライン交流イベント。これにちょくちょく参加させていただくうちに、急遽発表者(「乾杯の音頭」)がキャンセルになったということで、代打的に出演が決まりました。
主催者や、他のおなじみ様のご好意もあり、私が日本語学校で経験した様々な出来事、それもかなりハードな内容も含めて語っていいということで、手探りの中、人生で初めてのWebセミナーを担当したのです。
元来の行政書士という立場、そして勤務校との契約というのもあって「守秘義務」との兼ね合いが難しところではあるのですが、あくまで私個人の経験談ということで、赤裸々なエピソードをいくつか披露しました。拙いしゃべりでお聞き苦しかったところでしょうが、お聞きいただいた方から「とんでもねえ話を聞けて楽しかった」という声をいただきました。
進路イベントで基調講演を初体験
続いて2024年5月、株式会社アクセスネクステージ主催の進路イベント(日本語学校と大学・専門学校との情報交換会)で、「日本語教師の新しい働き方」についての講演をさせていただくことになりました。これはもともと、同社の担当者とコミュニケーションをとっていく中で、私が勤務校で開発した「日本語学校情報処理システム」についてその方が興味をお持ちになり、「ぜひ先生の新しい取り組みを業界の先生に紹介してほしい」ということで始まった企画でした。
一生懸命話して、私の取り組み事例を紹介しました。情報処理の工夫や、業務改善の考え方など、私が思うところを語りました。45分程度喋りましたが、なかなか準備していたことがすべて収まらず、駆け足になってしまったことを反省しています。ここで学んだのは、日本語教師の悩みやニーズはさまざまなので、日本語教師同士のコミュニケーションの場をもっと見出して、個人同士で情報交換することが大切だということです。
シリーズ続編として、今回の講演へ
本日私がお話することは、この株式会社アクセスネクテージ主催イベントでの講演をベースに、その後考えを深めたことの紹介です。講演をお引き受けしたのが7月頃。数ヶ月たてば、またいろいろ考えが変わったり、加わったりしているだろうなと予想はしていましたが、その通りでした。春は新学期ということもあり、業務改善に向けて鼻息荒いのが私の一年間のバイオリズムですが、秋ぐらいになるとまた経験を積み重ねたせいか、なにかについてこうあるべきです!とテーゼを投げかけることが少々気恥ずかしくなり、どのようにメッセージを伝えたらいいか悩んだところです。
まとめ
日本語教師を「芸人」に例えれば、日本語学校などは「芸能事務所」であり「劇場」です。日本語教育業界を盛り上げていただいている企業各社は「テレビ局」のような存在で、日本語教師が様々情報発信をしたり、学校同士、個人同士でコミュニケーションする機会を創っていただいています。
このような機会をこれからもさらに拡大し、留学生にとって日本語教育の最初の入口である日本語学校の日本語教師個人からの声が、業界全体を盛り上げる一つの要素になればと思います。
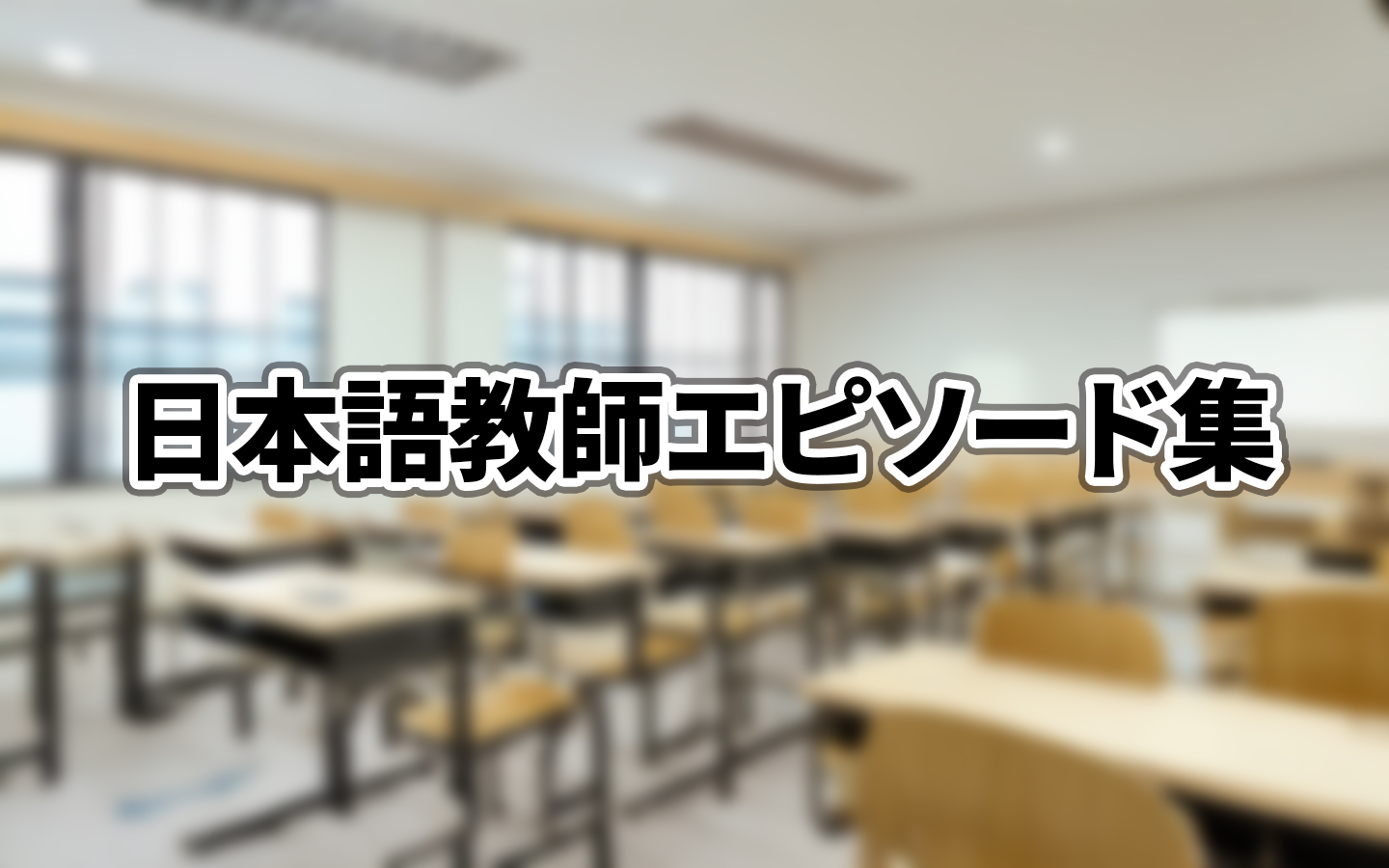

コメント