この記事では、2024年11月8日に株式会社ライセンスアカデミー主催の講演会でのテーマについて補足情報をまとめています。お聞きいただいた先生方のに共有する資料として執筆しました。
日本語業界の何が「激動」しているのか
自分で講演テーマを設定しておいて、いきなり前提を疑うような見出しです。これは、2024年5月に株式会社アクセスネクステージ主催のイベントで講演した際に設定したテーマと同じもので、一応シリーズとしての位置づけで今回も設定させていただきました。
実は日本語教師個人にとってはまだ「激動」を感じる段階ではないかもしれません。すでに日本語教育機関で教壇に立っている先生からすれば、なにやら制度が変わるんだなぁという程度のものですが、日本語学校の設置者や経営者、校長先生や教務主任からすれば「認定登録日本語教育機関」の申請に向けての準備追われることになり、「激動」を感じているかもしれません。
今回私が提案したい「視点」は、国家レベル、国際的なレベルのでの日本語教育ということでもなく、日本語学校の経営や運営というレベルのものでもありません。あくまでも、日本語教師個人の目線で、目の前の悩みを解決し、ニーズを形にしていこうという小さな一歩に向けて、日本語教師同士でコミュニケーションを取っていきたいという気持ちの表明です。
日本語教師の「新しい働き方」とは
ド新人ではないにしても駆け出しというわけでもない私。「新しい働き方」なんて偉そうなことを語れる立場ではないことは重々承知しております。しかし、「新しい働き方」に対する「旧態依然とした働き方」という概念を立ててみると、その間でまだ彷徨いながらも、新しくなった方がいいよね、という漠然とした考えを持っていることには違いありません。
世の中の会社やサービスは「DX化」なんて言葉が流行っていて、DXすなわちデジタルトランスフォーメーション、コンピュータでうまいこと自動化して仕事が効率的に進んでいく、と言われています。AI(人工知能)の進化も目覚ましく、コンピュータとの付き合い方は、日本語業界だけの話ではないですね。
DX化というハイレベルな話ではなくて、ちょっとしたIT化という点についても、日本は世界に遅れをとっていると言います。世界っていってもどの国のことだよって言いたくなりますが、おそらくはアメリカや中国、ヨーロッパのイケイケの企業が開発している便利なアプリの前には、日本の仕事の現場はまだまだ遅れているということで納得しておきましょう。
日本語学校で扱う「データ」というものは、実はそれほどたいしたものではありません。経営データなどは所管外ので割愛しますが、成績データや出席データというものについても、たしかに管理には手間がかかるものの、データ構造としてはシンプルです。適切なデータベースの作り方をはずさなければ、十分に管理可能なものです。
問題となるのは、組織や所属する人間同士のITスキルの差や経験値、考え方の違いに由来するIT化へのハードルです。授業引き継ぎをどのように記録するかを考えてみましょう。Aタイプの先生は、「授業の引き継ぎなんてノートに書いておいて、準備する前に次の担当の先生が読めばいいと言います。Bタイプの先生は、「授業引き継ぎはメールやメッセンジャーで共有できるようにExcelやWordなどのデジタルデータの方がいい」と考えます。Cタイプの先生は、ExcelやWordは、パソコンによってバージョンやライセンスの問題も発生するので、Googleスプレッドシートにまとめて、クラウドにして管理するのがいい。メッセンジャーも、LINEでスマホがパンクするよりもSlackのようなコミュニケーションツールを採用した方がいい」と考えます。
私の勤務校は、同僚教師の協力もあって、Cタイプまでたどり着きました。授業の準備のための材料をすべて電子化して①Google Driveに保管してあります。そして、事務連絡を②Slack(LINEと旧TwitterXの中間のようなアプリ)でテーマ別に行い、授業記録をデータベース機能に優れたノートツールである③Notionに記録する。この流れが確率しました。これはコロナ禍後に開校した新規校で、新しい先生が多かったからこそ実現した業務改善の成功例かもしれません。必ずしもすべての業務を高度にIT化する必要があるわけではないと、ソフトな立場を取る私ですが、ワークシートのコピーをとりにわざわざ学校に交通費と時間を書けてきたり、二度手間な仕事に時間を食われたりすることがなくなるわけです。
「旧態依然とした働き方」で非情にまずいものは、いわゆるブラック化を当然のものとみなしてしまう傾向です。残業が多かったり、パワハラが横行したり、給料がいつまでも上がらなかったり。給料については現場としてはどうしても文句をつけたくなるもので、経営者と被雇用者の戦いは永遠のものです。しかし、残業についてはあるよりないほうが学校としても先生としても利があります。パワハラなんてのはもってのほかで、令和でそんなことをやっていたら先生にも学生にもそっぽをむかれてあっという間に潰れるでしょう。
理想的な働き方をする同僚の仕事っぷりを盗む
私の同僚は、実に仕事が上手です。残業0でビシっと毎日上がりながらも、期限はきっちりと守り、教務でも進路指導でも成果を残すスーパーな専任教師(若手女性教員)。他にも、ちょぴっと残業はしつつも、裏教務主任さながらの頼もしさで、教務を支える姉御肌。なんといっても最前線を突き進む先生がホワイトに働いていることは、新しい先生にも波及していいサイクルを生み出しています。
「新しい働き方」を語りたいのは、私の働き方がいいぞ、なんて自慢したいものでは全くありません。そうではなくて、上手な働き方をしている日本語教師を見た時に、いかにそれを盗んで、助けて、他の人に波及させるか、そういったところに、私は個人的にやりがいを見出しています。
今、例に上げた女性の先生は、もともとITが得意というタイプではありませんでした。しかし頭は柔軟、人に質問するのも、自分なりに他人のアドバイスを活かすのもうまい。IT関連の知識をどんどん吸収していくので、私もまけられないと最新知識を学習するよう刺激されたものです。
まとめ
本講演においては、話し手ある私からもエピソードを紹介してまいりますが、聞き手である先生方からもこのような「先生同士で参考にした」というよう働き方改革の事例をいただけたらと思います。悩みや課題解決のニーズが浮かび上がった時、私はこうしているよ、あなたの仕事を盗ませてね、というような、前向きなコミュニケーションをどんどん活性化していくことが、楽しくてホワイトな職場を作っていくことにつながっていくのです。
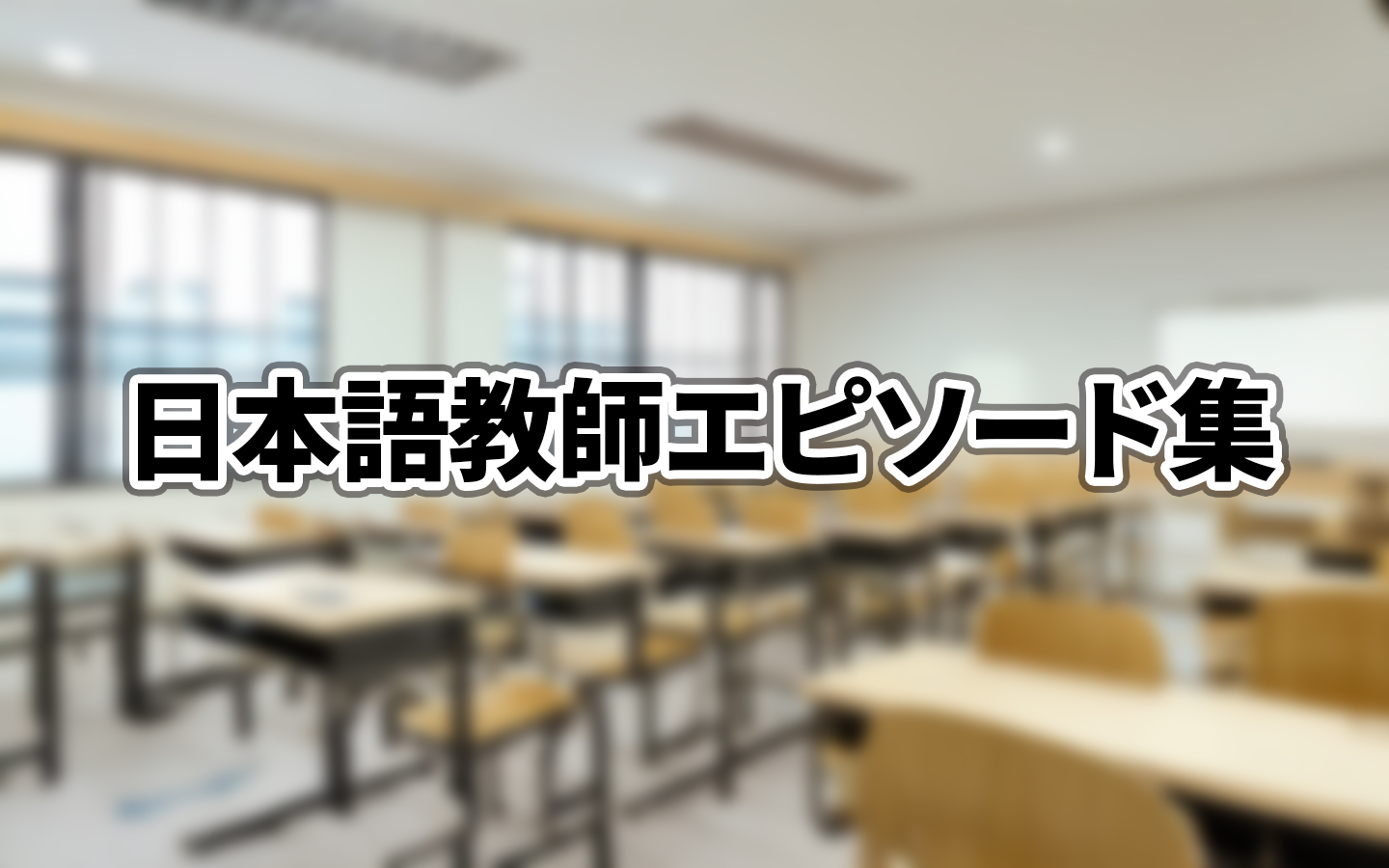

コメント