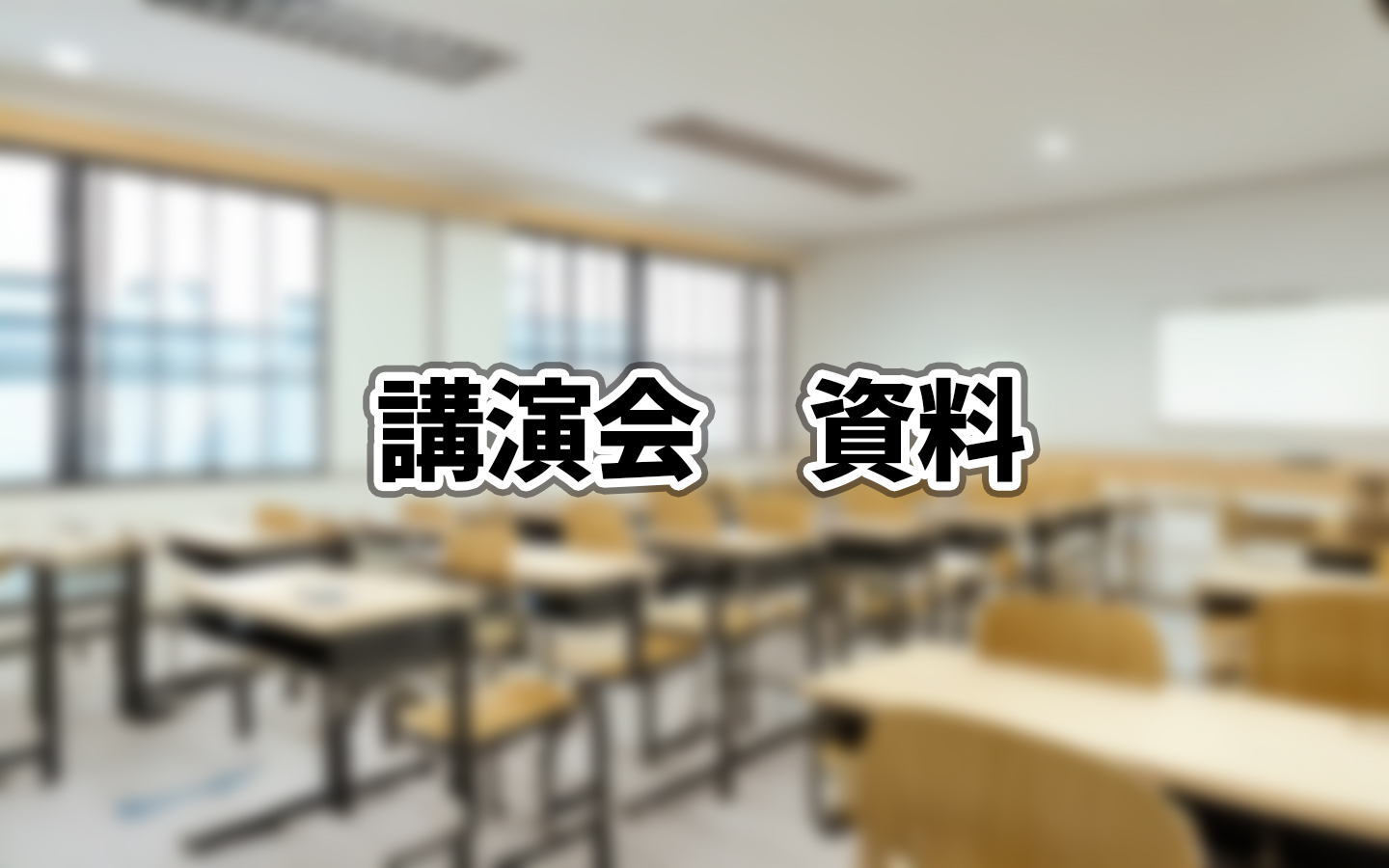このページは、2024年11月06日に株式会社ライセンスアカデミー大阪支社主催「日本語学校教員と上級学校(各大学・短期大学・専門学校)との個別情報交換会」における基調講演のまとめです。
基調講演は30分間という限られた時間ですので、伝えたいことをもれなくお話することができません。参加者の方々が、講演の最中や終了後に、補足として御覧いただけるにまとめた記事のまとめです。
各記事は、ブログ形式で順次アップロードしたページにリンクされています。興味を持たれた項目をクリックしていただいて、オムニバス形式でお楽しみいただければ幸いです。
01.自己紹介
一言で:「学生時代から言語好きだった氷河期世代の男が、職を転々としながら宅建士、行政書士になり、気づけば日本語学校で日本語教師にどっぷりと浸かり始めていたという話」
02.テーマ
一言で:「激動する日本語教育業界における、日本語教師個人としての新しい働き方」
03.講演をお引き受けしたきっかけ
一言で:「『留学生支援』を掲げる企業や公的団体の取り組みに関わる中、『日本語教師個人』の本音を共有するコミュニケーションの機会が少ないと感じ、日本語学校の現場最前線で働く者としての悩みやニーズを先輩先生方に投げかけることで、日本語教師の新しい働き方を摸索するきっかけを生みたいと考えた。」
04.日本語教師の「悩みとニーズ」〜個人の視点から問題提起〜
一言で:「マクロな視点も重要だが、まずはミクロな視点で日本語教師という仕事について考えたい」
日本語教師と一言に言っても、仕事をする機関によってそのあり方は様々です。「日本語教育」という大きなテーマで語ると、どうしても国家の政策的な視点や、日本語教育機関の経営・運営的な視点での議論なりがちで、いつのまにか「教師個人」の感覚が忘れられてしまっているような感覚に陥ります。
日本語教育全体での改善を目指すにはトップダウン的な議論がもちろん必要なことですが、今目の前の課題や問題を解決し、教師個人が幸せにむかって仕事をしていくために、時には「個人の視点」から率直な情報共有をして、ボトムアップ的な解決を図ることも大切なのではないかと考えました。
05.日本語教師の「アスペクト」〜各局面における苦労〜
一言で:「日本語教師は、なるのも、はじめるのも、続けるのも大変な仕事。」
06.日本語教師の「危機管理」〜有事に備えた平時のとりくみ〜
一言で:「一般企業と同じく、日本語教師にも『危機管理』が必要。危機への備えをスキルに変える。」
日本語教育に関わる人々を、「危機」主体で列挙すると
- 日本語学校の危機
- 日本語教師の危機
- 日本語学校の留学生の危機
という見方になります。
第一に、学校という組織のには、経営難や不祥事など様々な要因での危険(リスク)があり、危機は絶対に怒らないということはありません。しかし、今回は日本語教師個人の視点によるお話なので、経営者目線の議論は割愛します。
第二に、日本語教師の危機といえば、職を失わないかということよりも前に、時として「命」に関わる危機もありえます。私が人生で初めて命の危険を感じた事件について、回想していきます。
第三に、学生が巻き込まれる事件、事故、被害または、加害者の方になってしまう可能性という文脈での「危機」です。こちらもエピソード毎に、回想していきます。
07.日本語教師の「理想的な働き方」とは〜ホワイトな職場へ〜
一言で:「超絶ホワイトな働き方を実践していまっている同僚日本語教師が存在している」
超絶ホワイトな働き方を実践していまっている同僚日本語教師が存在している件
08.悩み解決のための取り組み事例
一言で:「小さな仕事の工夫を自慢しあい、共有してパクリあうことで、日々「i+1」の仕事改善。」
ある日本語教師の本音「なんだかんだで日本語教師をやってきたが、実は日本語の文法など不安なところがある。」
「餅は餅屋」、ならば「日本語教師は日本語屋」ということで、日本語教員試験に乗っかって、知識を仕入れ直そうとFルート受験を決意した件
続きはブログで
09.本講演主催者への今後の希望
一言で:「日本語教師に『コミュニケーション』の場を今後も多く創っていただきたい。」
日本語教師を「芸人」に例えると、所属する学校は「芸能事務所」や「劇場」と言えるでしょう。また、今回のイベントを主催していただいた企業は、日本語教師を始め、留学生が今後活躍していくためのきっかけの舞台をつくってくれる「テレビ局」のようなものです。
私の勤務校は、株式会社ライセンスアカデミーに加えて、株式会社さんぽうや、株式会社アクセスネクステージとのお付き合いが深まっていて、毎回留学生の進路イベントでお世話になっています。「テレビ局」は異なっていても、様々な「楽屋」で「他事務所の芸人さん」とお付き合いが始まることがおおく、普段の自分の出演する「劇場」を一歩出てコミュニケーションをとることは大変意義があります。
ともすれば世間知らずになってしまいがちな忙しい日々にあって、今回のようなイベントを拡充し、日本語教師個人の視点も取り入れながら、新しい先生の誕生や、現職の先生のさらなる活躍、そして日本中に広義の「日本語の先生の輪」が広がっていくことを願ってやみません。
続きはブログで
10.まとめ〜質疑応答・フィードバックへの返答〜
一言で:「新しい先生や、先輩先生方とのコミュニケーションで、新しい働き方のヒントを得る。」
私が経験した事件・事案は、どれも「新規校ならでは」のものばかりで、伝統がある学校やベテランの先生方の視点が不足しています。どの学校もこれからこういうことに苦労するから備えておいた方がいいよというアドバイスを賜われれば、各局面で頑張っている先生の励みになるでしょう。
様々なエピソード、大小問わず、お仕事の悩みの解決事例等のご提供をお待ちしております。
続きはブログで
オムニバス「日本語教師エピソード集」
日本語教師になるまで編
新任日本語教師編
デビューは突然やってきた事件
直接法、語彙コントロールって何?事件
「やんちゃな学生をどうしたらいいのか」事件
新規校実務編
市販のシステムが高すぎるので自分で作ってしまった件
データ分析をしようと思ったが、日本語学校のデータって何?事件
認定日本語教育機関に向けた準備編
結局、カリキュラムどうするのよ事件
日本語学校実務・IT活用編
手間のかかる仕事は、プログラミングで片付けた方が絶対にいい件
外国人留学生とのコミュニケーション蓄積編
留学生が「先生」よりも「先輩」を信じる理由
「はい先生」「ない先生」「だいじょうぶ先生」の三段階
危機管理編
女子学生の同郷彼氏DV&教師に対する暴行傷害事件
ウズベキスタン騒動
不動産詐欺被害事件