この投稿では、練習問題から「言語と教育」の分野で抑えておきたい知識について、私のノートとして記述します。箇条書きで必要な知識を列挙して、【すみカッコ】にわたしの心の中のツッコミをメモしていきます。
第1回
絵カード・レアリア
- 絵カードはシンプルなものがいい【不要なものを消せるのが長所】
- 絵カードには、字を入れないほうがいい【余計な情報は入れない】
- すべてレアリアである必要はない【いろいろ使っていい】
- レアリアは全て著作権の許諾が必要というわけではない【使えるものは使う】
コンピュータを利用した教授法
正解
- CAI = Computer Assisted Instruction
間違いの選択肢
- TPR = Total Physical Response
- ASTP = Army Specialized Training Program
- CLL = Commuity Language Learning(カラン)
ウォルター・リップマン『世論』
「自分以外の人たちの行為を十分に理解するためには、彼ら自身が何を知っていると思っているのかを知らなければならない。」
ハイデッガーのロゴスに関する考察
- 類型化(カテゴリー化)
アセスメント(評価)
要するに、留学生について様々な角度から測ること。
他の選択肢
- トリアージ(選別)
- セレクション(選択)
- エンリスト(リスト化)
スピード
教師の判断に求められるのは、妥当性とスピード
他の選択肢
- タイミング
- 価値観
- 積極性
読む能力と書く能力
日本でアニメを日本語で見たいというニーズを持っている学生に必要な能力
他の選択肢(ここでは必要がない能力)
- 読む能力と話す能力
- 書く能力と読む能力
- 聞く能力と書く能力
アニメを見たい学生に必要がない授業
- 漢字の書き取り
他の選択肢
- ディクテーション(聞いて、そのまま書く)
- 縮約形の学習
- ミムメム練習(音声を聞いて、そのまねをして覚える)
著作権
- テレビは教育機関(一条校)で教育目的ならばOK
- 私塾は注意
- 教育機関で、教師が授業のために市販のテキストをコピーすることは、著作権に抵触
学生のグループ分けの際の配慮
- 宗教的・政治的対立についての配慮を教室の中まで持ち込む必要はない
- 公平であることが大切(公平でないやり方が「誤り」となる)
ジグソー
段落を組み合わせる
他の選択肢+1
- シャドーイング(聞いて、書く)
- ボトムアップ(読解で、小さな意味から組み立て、最後に全体をとらえる)
- トップダウン(先に理解する)
- スキャニング(読解で、自分が必要としている情報だけ探し出す)
- スキミング(ポイントを拾い読みしていく)
媒介語
- 学習しようとする言語は、目標言語
- 説明や解説、活動の指示などで用いられる言語を媒介語
文法訳読法
読んで訳す勉強法
他の選択肢
- サジェストペディア(ロザノフ)
- オーディオ・リンガル・メソッド(1960年代前半まで)
- サイレントウェイ(ガッテーニョ・1970年代)
プレースメントテスト
クラス分けテスト
その他の選択肢
- アチーブメントテスト(到達度テスト→期末テスト)
- プロフィシェンシーテスト(熟達度テスト、能力度テスト→実力テスト)
- クローズドテスト(一部空欄の形式のテスト)
何度行っても同じ結果→「信頼性」が高い
そのテストが測ろうとした能力を測っているか→「妥当性」
正規分布
山型のグラフ
キーワード
- メジアン(中央値)
- 分散
- 標準偏差
- 得点分布
コンフリクト
異文化コミュニケーション上でぶつかり合いが起こることは避けられない。
コンフリクトが起きたこと否定するのではなく、むしろ行きた教材として利用する
ビリーフ
語学学習に対して持っている信念
他の選択肢
- アクション・リサーチ(教師の成長のための振り返りを行なう手法)
- ニーズ(学習者が求めるもの(
- ピア(同輩・仲間)→ピアラーニング、ピアライティング、ピアリーディング
ニーズ
ニーズ調査(ニーズアナリシス)
選抜的評価
入学試験
診断的評価
- プレースメントテスト
- アプティチュードテスト(適正テスト)
形成的評価
- 中間テスト
- 復習テスト
- 小テスト
総括的評価
期末テスト
客観テスト
←→主観テスト
弁別力(識別力)
点双列相関関係で、1.0から-1.0
高い能力を示すものほど、正答者が高くなる傾向を示す問題がよい問題となるという考え方
マイナスは、全体の点数が低い者がより多く正解していることを示す
第2回
発音の誤用 長音
時計 → とうけえ
同じ誤用
- 来て → きいて
- 歌手 → かあしゅ
- 正解 → せえかい
異なる誤用
- たくさん → たっさん(無声化した/ク/が、促音で発音されている)
発音の誤用 hの脱落
日本語 → ほおんご
同じ誤用
- おはようございます → おはようございます
- ご飯 → ごあん
- 見本 → みおん
異なる誤用
- 日本へ → にほね(母音の前の/N/の鼻母音を歯茎音[n]で代用したため、拍の誤りも)
発音の誤用 長音の脱落
スーパー → スーパ
同じ誤用
- コーヒー → コーヒー
- アカデミー → アカデミ
- ニュース → ニュス
異なる誤用
- アンケート → アンケット(長音が促音のカタカナ「ッ」で表記されている
漢字の読みの間違い 漢音と呉音
口調(くちょう) → こうちょう
同じ誤用
- 工夫(くふう) → こうふう
- 貴重(きちょう) → きじゅう
- 作用(さよう) → さくよう
異なる誤用
- 四月(しがつ) → よんがつ(音読み「シ」と訓読み「よん」の誤り)
「たい」と「ほしい」の誤用
自分の希望
- 勉強したい → 勉強ほしい
同じ誤用
- 帰りたい → 帰ってほしい
- 休みほしい → 休みたい
- 飲むほしい → 飲みたい
異なる誤用
- 見せてほしい → 見せほしい(他者の行為を求める文)
ナチュラルメソッド
幼児の言語習得課程を取り入れ、口頭表現を重視する教授法
他の選択肢
- オーラルメソッド(パーマー、直接法)
- ナチュラルアプローチ(テレルがクラッシェンの第二言語習得論を参考に開発した聴解優先の教授法)
- コグニティブアプローチ(チョムスキーの変形生成文法とキャロルに認知学習理論による教授法)
オーディオ・リンガル・メソッド(AL法)
ミムメム練習やパターンプラクティス
他の選択肢
- ゲーム
- シチュエーションドリル
- ロールプレイ
コミュニカティブアプローチ(CA)
- インフォメーションギャップ(情報差)
- チョイス
- フィードバック
この指導原理として、不適当な選択肢
- 構造シラバス
シラバス
- 構造シラバス
- 機能シラバス
- 場面シラバス
- 話題シラバス
- 技能シラバス
- タスクシラバス
フォーカス・オン・フォーム
ロングが提唱、コミュニケーション中心の活動の中で、言語形式にも意識を向けさせる教授法
その他の選択肢
- フォーカス・オン・ミーニング(コミュニケーション活動の中の意味交渉中心の教授法)
- インタラクション補強法(学習の相互交流によって言語形式を意識させる方法)
- フォーカス・オン・フォームズ(AL法のように文法などの言語形式に集中した教授法)
テスト
- 診断的評価(コース開始時)・・・プレースメントテスト
- 形成的評価(開始後)・・・小テスト、中間テスト
- 総括的評価(終了時)・・・期末テスト
アチーブメントテスト
学習項目がどの程度習得できたかを見る
- プレースメントテスト・・・クラス分けテスト
- アプティチュードテスト・・・語学学習の適正を測るもの
- プロフィシェンシーテスト(JLPTなど)・・・実力試験
評価
- 選別評価
- 測定評価
- 認定評価
- 外在的評価・・・学習機関ではない機関が行なうもの
- 相対評価・・・集団内の位置付け
- 絶対評価・・・集団にかかわりなく一定の基準で行なう
- 到達度評価・・・一定の到達目標を基準にする
- 個人内評価・・・ポートフォリオによる評価
信頼性
誰が何度やってもテストの結果が変わらないこと
その他の選択肢
- 妥当性(測りたい能力を見るのに適切かどうか)
- 実用性(時間、経費、労力など実際に実施できるか。経済性)
- 真正性(内容が実際の言語使用場面に合うか)
得点等化
- 総合的測定法(全体的に見て評価)
- 分析的測定法(発音や文法など項目に分けて評価する)
- 集団準拠テスト(NRT、集団の中での相対的な位置付けを目的)
- 目的準拠テスト(CRT、受験者ができることや学習の伸びを見るもの)
- 項目分析(出題項目が適切かどうかを調べること)
- 得点等化(難易度を補正)
再配列法
正しい順に並べ替える
他の選択肢
- 多肢選択法
- 真偽法
- 組み合わせ法
客観テスト
- 再生形式(解答を書き込む)
- 単純再生法(空欄に記入)
- 訂正法(誤りを訂正)
- 完成法(文を完成させる)
- 変換法(指示に従って書き換える)
- クローズド法テスト(ある文章に一定の間隔で作られた空欄にあてはまる語を記入する)
コンテクスト(文脈)
- 高文脈(ハイコンテクスト)・・・日本、アラブ
- 低文脈(ローコンテクスト)・・・ドイツ、スイス、アメリカ
CMC(Computer Mediated Communication)
コンピュータを媒介とするコミュニケーション
他の選択肢
- CMI(Computer Managed Instruction, 教師がコンピュータを使う)
- CAI(Computer Assisted Instruction)
- CBT(Computer Based Training)
著作権法
第35条(学校その他の教育機関における複製等)
第三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行い、又は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2前項の規定により公衆送信を行う場合には、同項の教育機関を設置する者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
3前項の規定は、公表された著作物について、第一項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合において、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信を行うときには、適用しない。
第36条(試験問題としての複製等)
第三十六条 公表された著作物については、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。次項において同じ。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2営利を目的として前項の複製又は公衆送信を行う者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
CEFR(Common European Framework of Reference for Languages)
ヨーロッパ言語共通枠
背景:行動中心アプローチ
構造主義から行動中心主義への転換
他の選択肢
- 本質主義
- 構造主義
- 構造主義
【足りないところを学ぶというより、学習者に必要なことを学ぶ、という方向性】
多文化共生
コンフリクトの対処
【知識というより、問題文を読んで、日本語教師としてどうするべきかの適切な立場を記述した解を導く】
コースデザイン
学習を開始する前に、指導項目、教授法、指導順序、評価の方法を決めるもの
- ニーズ調査
- レディネス調査
- 適性テスト
- 目標言語調査
- ビリーフ調査(学習者の考え方)
他の選択肢
- シラバスデザイン(学習項目を決める)
- カリキュラムデザイン(授業配分、教材と進度、評価の時期と方法を決める)
- レッスンプラン(日々の授業内容を決め、各授業の時間配分や教材、手順を考えたもの)
- インストラクショナルデザイン(学習効果が高い学習計画を立てること)
教師トレーニング
規範となる教え方ができるようにトレーニングをすること。
これにあたらないもの
- アクションリサーチ(先生が内省をする工夫)
- ティーチングポートフォリオ
- ケーススタディ
【上記3つは、「教師が自身で成長する」という考え方】
インプット仮説
学習者のレベルより少し上の情報を与えて習得させる
他の選択肢
- モニター仮説(学習で得た文法知識は言語使用の際に正しい文を作るよう意識させる)
- 習得・学習の仮説(自然なコミュニケーションにより無意識に学ぶ習得と文法などを意識的に学ぶ学習は異なる)
- 自然順序仮説(言語習得には自然な順序がある)
- 情意フィルター仮説(学習者の不安や心理的な障害があるときは学習効果が上がらない)→ナチュラルアプローチ開発
記憶
- 短期記憶
- 長期記憶
- 宣言的知識(事柄について言葉で説明できる知識)
- 意味記憶
- エピソード記憶
- 手続き的知識(運用するための技能としての知識)
- 宣言的知識(事柄について言葉で説明できる知識)
【「覚えた語句や表現が実際の場面で使えるようになる」ということは、宣言的知識が手続き的知識に移行するということ】
明示的学習法
学習者の希望を入れて講師が学習内容を決めて指導する
他のキーワード
- 状況的学習論
- ファシリテーター
- スキャフォールディング、足場がけ
スキーマ(背景知識)の活性化
学習内容に関する学習者の背景知識
他の選択肢
- アカデミックジャパニーズ(高等教育機関での専門的な学習・研究に必要な日本語力)
- キーワード法(記憶の方法)
- LAD(言語獲得装置、チョムスキーらが唱えた、人が生まれた時から持っている言語を獲得する能力のこと)
ジグソー学習
分担して読んだものを、情報交換して全体を把握する
他のキーワード
- ピアリーディング(協働して学習)
- エバリュエーション(アンケートやインタビューを行って教育の成果を評価)
- タスクリーディング(指定された情報を文章から探し出す読解)
- スキャンニング(その読みの作業)
- スキミング(文章の大意をとる読みの作業)
- 情報リテラシー(情報を活用する能力)
ボトムアップ処理
語句や文型の意味を理解してから各文の意味を理解し、その上で文章全体の意味をつかむ読み
他の選択肢
- トップダウン処理(逆に、大意を取ってから、一分ずつの意味を確認する読み)
- リキャスト(その場ですぐ言い直すこと)
- ピアレスポンス(協働学習の一つ)
聴解とスキャニング
必要な情報を聞き取る聴解
他の選択肢
- スキミング(大意)
- ディクテーション(聞いてそのまま書く)
- シャドーイング(聞いてそのまま言う)
言語間エラー
母語と目標言語の間の違いで起こる誤り
キーワード
- 言語内エラー(目標言語内の誤り)
- ローカルエラー(意味の伝達に支障がないもの)
- グローバルエラー(コミュニケーション上問題があるもの)
- 母語の干渉(母語の影響による誤り)
【そのエラーが、言語内か、言語間か、ローカルかグローバルか】
インターアクション
学習者間の発話のやりとり
他のキーワード
- ターン(それぞれの発話の機会)
- ディスコースマーカー(会話をつなぐサイン)
日本語指導の必要な外国人児童生徒
- ポルトガル語(ブラジル)
- フィリピノ語(フィリピン)
- スペイン語(ペルー)
他のキーワード
- 帰国児童生徒(一時期海外で過ごした後に帰国した日本人の子ども)
言語相互依存仮説
カミンズ提唱、言語学習能力において母語と第二言語の二言語は、相互に影響し合う。日本語能力を伸ばすと同時に、母語による強化学習も併せて支援することが有効であるとする。
他の選択肢
- 普遍文法理論(チョムスキー、生成文法)
- 中間言語仮説(習得課程で持つ、母語とも目標言語とも違う規則をもった言語の体系)
- 臨界期仮説(ある時期にならないと)
(進捗メモ:ここまで31/61ページ)
第3回
撥音の誤用
さんねん(三年) → さねん
同じ誤用
- はんにん(犯人) → はにん
- かんのん(観音) → かのん
- こんなん(困難) → こなん
異なる誤用
- さんねん(三年) → さねん
場所「で」の誤用
公園であそんでいます → 公園にあそんでいます
同じ誤用
- カフェで待っています → カフェにまっています
- 図書館で宿題をします → 図書館に宿題をします
- レストランで食べましょう →レストランに食べましょう
長音の誤用
レポート → レポト
その他の誤用(鼻音)
- からしがはいっている → かなしがはいっている
- かならず(必ず) → かななず
- りんご → にんご
- かるい(軽い) → かぬい
文字の有無の誤用
こうえん(公園) → こえん【うの脱落】
その他の誤用
- けいざい(経済) → けえざい
- おおきな(大きな) → おうきな
- うでどけい(腕時計) → うでどけえ
- こうじょう(工場) → こおじょう
並列関係の誤用
- 広くて豪華 → 広いと豪華
- 安くて便利 → 安いと便利
- 掃除をして買い物をします → 掃除をすると買い物をします
- 頭が痛くてのどが痛い → 頭が痛いとのどが痛い
その他の誤用
- もし雨がふったら映画に行きましょう → もし雨がふると映画に行きましょう
教授法の流れ
- 文法約読法(ラテン語)
- ナチュラルメソッド
- サイコロジカル・メソッド(幼児のように、グアン)
- 【聞く⇨話す⇨読む⇨書く】
- ベルリッツ・メソッド【媒介語禁止】
- サイコロジカル・メソッド(幼児のように、グアン)
- 直接法
- オーラルメソッド(パーマー)
- GDM(絵で見る〜語)
- 構造言語学・行動主義心理学
- ASTP(アーミメソッド、フリーズ)
- AL法(オーディオリンガルメソッド)
- 心理学・認知学習理論
- サイレントウェイ(先生静かにして、ガテーニョ)
- CLL(コミュニティ・ランゲージ・ラーニング、カラン)
- TPR(全身反応教授法)
- サジェストペディア(暗示式教授法、ロザノフ)
- 第二言語習得研究
- ナチュラル・アプローチ(クラッシェン)
- コミュニケーション
- コミュニカティブ・アプローチ
- タスク中心の教授法
言語の四技能
- 受容
- 聞く
- 読む
- 産出
- 話す
- 聞く
試験
- JLPT(The Japanee Language Proficiency Test、日本語能力試験)
- ACTFL-OPI(The American Council on the Teaching of Foreign Languages、会話テスト)
- HSK(中国政府公認の中国語のテスト)
フィードバック
- 明示的フィードバック
- 「上手にできましたね。」
- 暗示的フィードバック
- 非理解を示すフィードバック
アクセントなど
- 日本語のアクセントは「高低」アクセント
- 英語のアクセントは「強弱」アクセント
- 日本語は「有声音・無声音」
- 中国語は「有気音・無気音_
(進捗メモ:ここまで41/61ページ)
第4回
誤用の種類
- 仮名の図形認識の誤用
- クラス ⇨ ワラス
- 発音の不正確さが表記に反映した誤用
- フォーク ⇨ ホーク
- 語中の撥音が後続母音と結合して形成した誤用
- げんいん(原因) ⇨ げにん
- 「思います」とするべきところを「思っています」とする誤用
- あの店はもうすぐ開店すると思っています。
- 意向形にするべきところを辞書形を使った誤用
- 旅行に行くと思っています。
- 可能形を使うべきところで、辞書形を使った誤用
- たくさん漢字を勉強したので漢字が読むようになりました。
- 自動詞を使うところを他動詞を使った誤用
- このお皿は落としても割りません。
フォーカス・オン・フォーム
言語形式と意味交渉のバランスを重視する考え方。
TBLT(Task−based Language Teaching、タスク中心の教授法)
他の選択肢
- フォーカス・オン・ミーニング
- ナチュラルアプローチ
- イマージョン
- CBI(Content-based instruction、内容重視の言語教育)
- フォーカス・オン・フォームズ
- 言語形式を重視する考え方
- オーディオ・リンガル・メソッド
- TPR(Total Physical Response、全身反応教授法)
- ASTP(Army Specialized Training Program、アーミーメソッド)
後光効果
ハロー効果ともいう。
他の選択肢
- 系列効果
- 中心化傾向
- 寛大性傾向
言語的挫折
学習者が発話に窮した状況。試験のときに手助けをしてしまうと、言語能力を正しく測定できない。
略語整理
- VOD = Video On Demand
- CMI = Computer Managed Instruction
- CMS = Conputer Management System
- LMS = Learning Management System
練習
- 拡張練習
- 代入練習
- 変形練習
- 応答練習
学習者オートノミー
学習観の変遷
- 教育
- 支援
- 共生
- 自立
教師は、リーダーシップから支援者あるいはファシリテーターへ
文化変容モデル
ベリー、文化変容(acculturation)
- 同化
- 分離
- 統合
- 境界
他の選択肢
- 原因帰属
- ジョハリの窓
- モニター理論(クラッシェン、ナチュラルアプローチ)
- 習得-学習仮説
- モニター仮説
- インプット仮説
- 自然順序仮説
- 情意フィルター仮説
エポケー
判断停止、判断留保
相手の行動に対して即座に判断したり評価したりすることを控えること
他の選択肢
- エンパシー(共感)相手の立場に立って考える
- シンパシー(同情)自分の立場から考える
- エンパワーメント(自分の内なる力や可能性を全面的に発揮できるような環境や人間関係を構築していくこと)
アクティブリスニング
傾聴、能動的な聞き方
学習者からの相談などに対してすぐに解決策を与えたり、アドバイスをすることなく、学習者の話を積極的な姿勢で聞くことに徹することで、学習者自身の内面的な変化を促すスキルのこと
ボディーバブル
- バーンガ
- アルバトロス
- バファバファ
プロクセミックス(近接空間学)
他の選択肢
- パラランゲージ(パラ言語、準言語)
- 話す速度や音声の高さ・大きさといった言語音の周辺要素のこと。
- キネシクス(動作学)
- ジェスターやアイコンタクト
- プロクセミックス(近接空間学)
- 対人距離や空間的な縄張り意識を研究対象とする
- クロネミックス(時間学)
- 個人や文化圏が持つ時間間隔を研究対象とする
EPA
EPA = Economic Partnership Agreement、経済連携協定
他の選択肢
- FTA = Free Trade Agreement、自由貿易協定
- TPP = Trans-Pacific Partnership、環太平洋パートナーシップ協定
- ODA = Official Development Assistance、政府開発援助
シャドーイング
他の選択肢
- ターンテーキング
- ミムメム練習
- ロッド(積み木、サイレント・ウェイ)
CRT
CRT = criterion-referenced test、目標基準準拠テスト
他の選択肢
- NRT = norm-referenced test、集団基準テスト、相対的
- ICT = Information and Communication Technology、情報通信技術
- OJT = on the job training
データ分析の尺度
- 名義尺度
- 間隔尺度
- 順序尺度
- 比率尺度
レファレンシャルクエスチョン
学習者自身について尋ねるなど、教師自身が答えを知らない内容について回答を求める質問形式
他の選択肢
- ディスプレークエスチョン
- オルタナティブクエスチョン
- イエス・ノー・クエスチョン
代表値
- 平均値
- 最頻値
- 中央値
これにふくまれないもの
- 偏差値
著作権「無方式主義」
著作権は特許申請のような手続きを経なくても、自動的に発生する
著作者の死後50年間
学習ストラテジー
- 直接ストラテジー
- 記憶ストラテジー
- 認知ストラテジー
- 補償ストラテジー
- 間接ストラテジー
- メタ認知ストラテジー
- 情意ストラテジー
- 社会的ストラテジー
JSP
JSP = Japanese for Specific Purpose、目的別日本語教育
他の選択肢
- JGP = Japanese for General Purposes、一般日本語教育
- JSL = Japanese as a Second Language、第二言語としての日本語教育
- ATI = Aptitude Treatment Ineraction、適性処遇交互作用
シラバス(再掲)
確定時期による分類
- 先行シラバス
- 後行シラバス
- 可変シラバス
項目の内容による分類
- 文法シラバス
- 構造シラバス
- 場面シラバス
- 機能シラバス
- トピック(話題)シラバス
- タスク(課題)シラバス
- スキル(技能)シラバス
- 概念シラバス
- 折衷シラバス
プロセスライティング
- 構想
- 構成
- 執筆
- 推敲
- 完成
他の選択肢
- パラグラフライティング
- ピアレスポンス
- フリーライティング
フェーディング
徐々に支援を少なくし、学習者を自立に導く段階
他の選択肢
- モデリング
- コーチング
- スキャフォールディング
(進捗メモ:61/61)
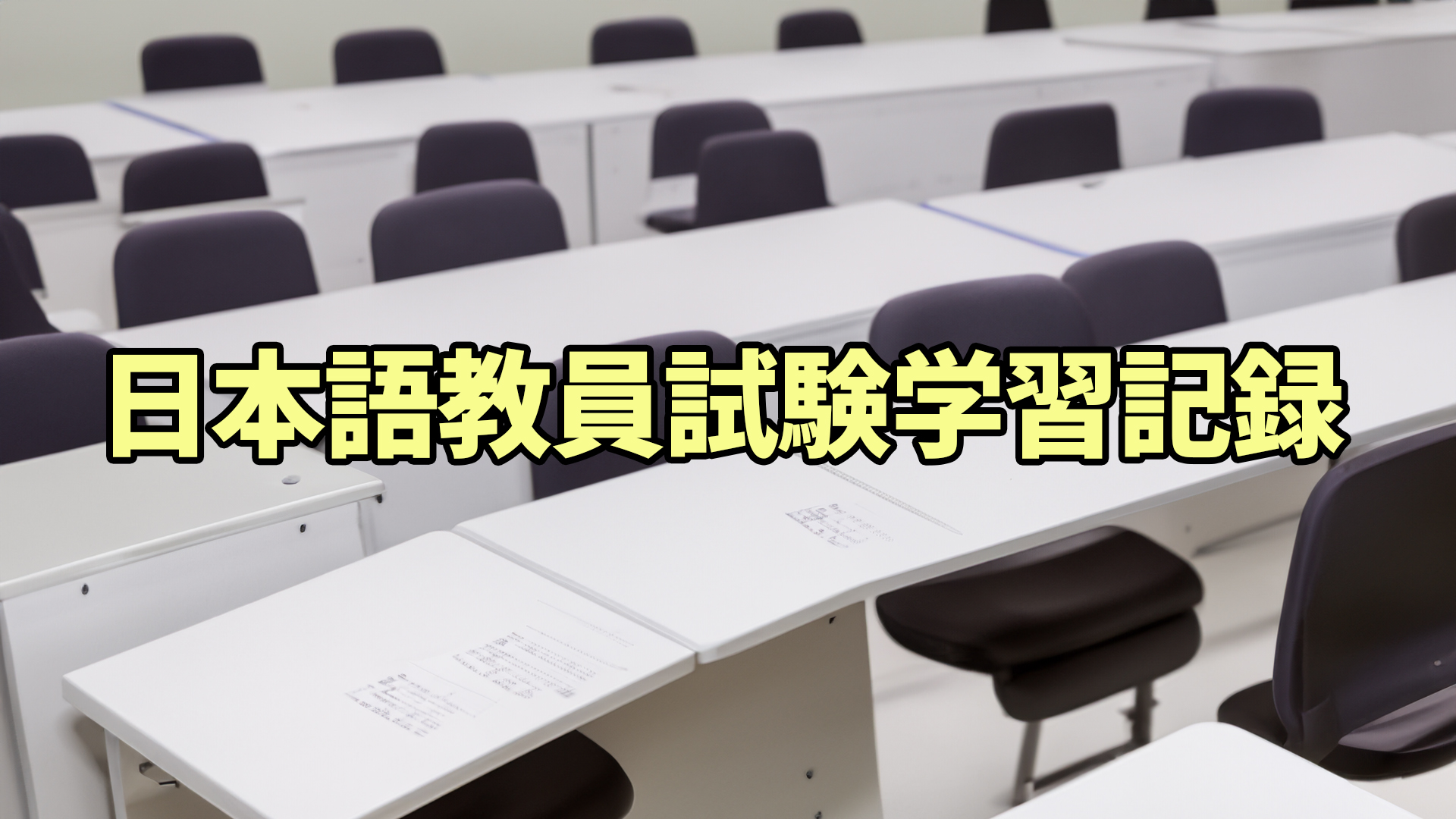

コメント