この投稿では、練習問題から「言語と心理」の分野で抑えておきたい知識について、私のノートとして記述します。箇条書きで必要な知識を列挙して、【すみカッコ】にわたしの心の中のツッコミをメモしていきます。
第1回
移行型バイリンガル教育
少数派言語から社会の中で優勢な多数派言語へ以降させること
他の選択肢
- 双方向バイリンガル教育
- 維持型バイリンガル教育
- 相続言語教育
知識
- 宣言的知識(事物や概念に関する知識で、意識し、言語化できる)
- エピソード記憶
- 意味記憶
- 手続き的知識(やり方に関する)
- 明示的知識(説明できる)
- 暗示的知識(直感的知識で、感覚的にわかっている)
インプット仮説
クラッシェン、学習者の現在の力よりほんの少し高いレベルのメッセージを与えることが最も効果的、i+1
他の選択肢
- モニター仮説
- 情意フィルター仮説
- 習得・学習の仮説
動機付け
- 道具的動機
- 統合的動機
- 内発的動機
- 外発的動機
フォーカス・オン・フォームズ
コンテクストから切り離された文法項目を一つずつ覚えていくような文法偏重の教室指導タイプ
他の選択肢
- フォーカス・オン・フォーム
- フォーカス・オン・ミーニング(ナチュラルアプローチやイマージョン、言語形式に意識を向けることを重視していない)
- フォーカス・オン・スピーチ
メタ認知ストラテジー
学習者自らが学習目的を明確にして、その実現のために学習計画を立て、実行し、評価するなどの方策を取ること
他の選択肢
- 記憶ストラテジー
- 情意ストラテジー
- 社会的ストラテジー
行動主義心理学
- 人間の行動の単位は刺激と反応の結合による習慣の形成である
整理
- 行動主義(何ができるようになったか)
- 認知主義(何がわかるようになったか)
- 状況主義・・2つに対するアンチテーゼ、すべてのものは状況に埋め込まれている
スキナー
- レスポンデント行動、パブロフの犬
- オペラント行動、餌がでるレバーを押すラットの自発的行動
その他の選択肢
- ヴィント(ドイツの心理学者、実験心理学の祖)
- ワトソン(アメリカの心理学者、行動主義心理学の創始者)
- ヴィゴツキー(旧ソ連の発達心理学者、人間の認知発達は社会的行為であり、歴史―文化的環境とは切り離せないものである)
罰
その他の選択肢
- 正の強化
- 強化子
- 負の強化
- 消去
記憶
- 符号化
- 貯蔵
- 検索
他の選択肢
- 潜在記憶
- メタ記憶
- 作動記憶(短期記憶)
MLAT
MLAT = Modern Language Aptitude Test、外国語学習テスト
他の選択肢
- BICS = Basic interpersonal Communicative Skills、日常言語能力
- CALP = Cognitive Academic Language Proficiency、認知言語学習能力
- ASTP = Army Specialized Training Program、アーミーメソッド、陸軍特別訓練プログラム
場独立・場依存
- 場依存の学習者は、全体的にものを見て、他人と一緒に学習するのを好む
- 場独立の学習者は、分析的にものを見て、一人で学習するのを好む
外向的・内向的
- 一般的に外向的な人は日常言語能力が高い
- 内向的な人と認知学習言語能力の相関はない
共有基底言語能力モデル
カミンズ、スワン提唱
2つの言語で共有されるのが認知言語学習能力
5,6年を要する
第2言語
2つの意味
- 第1言語を習得した後に学習する言語の意味
- その言語が社会の中でコミュニケーションとして使われているということで、外国語と区別
シューマン
文化変容モデル(Acculturation Model)
他の選択肢
- ロング
- ピネマン
- スウェイン
アコモデーション理論
ジャイルズ、学習者が目標言語集団と学習者集団の関係をどう意識しているかに注目
他の選択肢
- 経験説←→生得説
- 有標性差異仮説、エックマン、母語と異なりかつ有標性の高いものは習得が困難であるが、逆に、母語と異なっていても、有標性の低いものは習得が容易である
- 対照分析仮説、学習者の発話に見られる誤用の原因は、学習者の母語と第二言語の
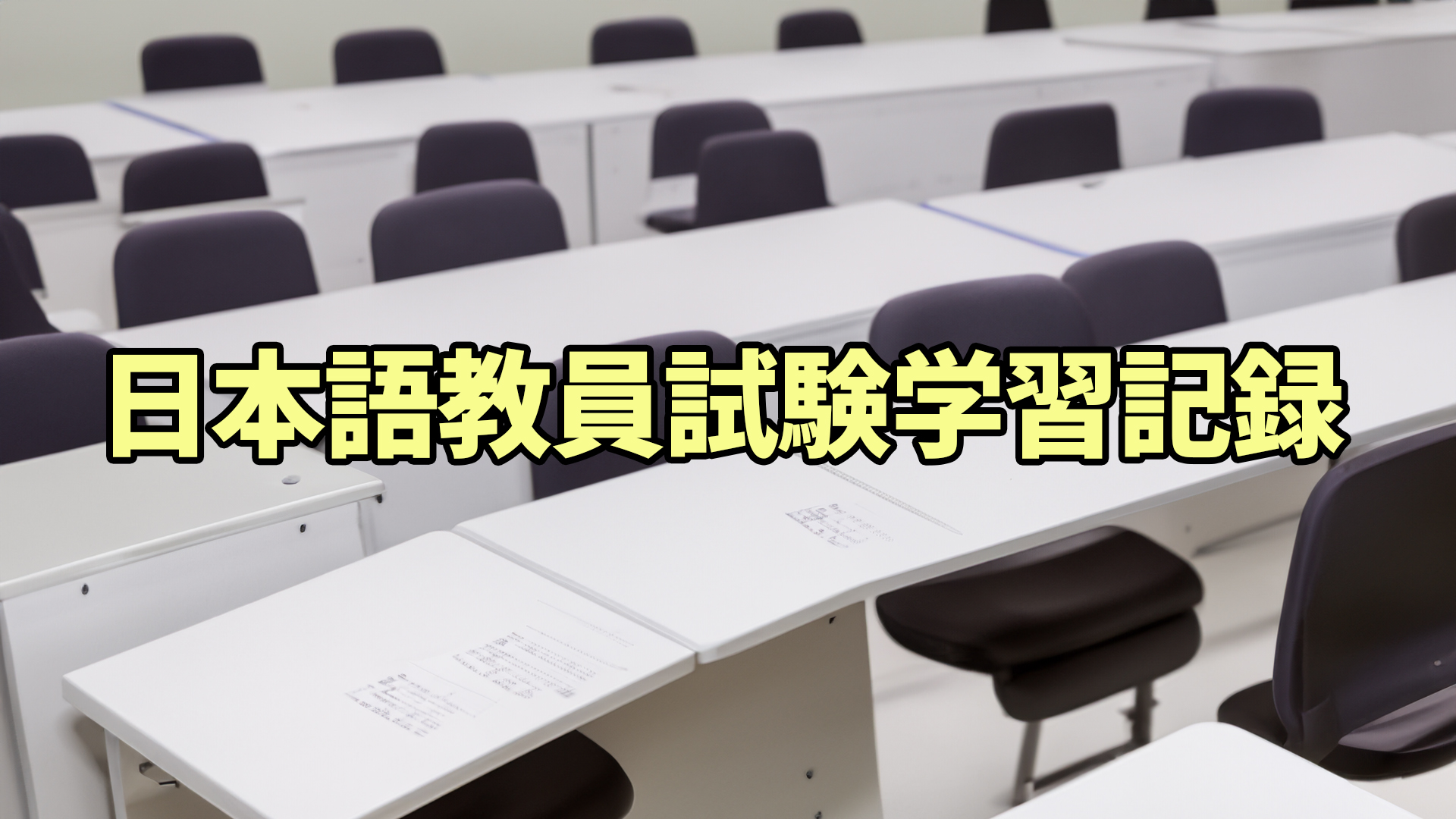

コメント