この記事では、私が日本語教師になるまでの歴史を紹介したいと思います。
言語に関する知識の背景
小中学生のころの私は、「ドラえもん」や「こち亀」などのマンガと、「ドラクエ3・4・5」にどっぷりはまった子どもでした。中学受験など1ミリも考えずお気楽な時代だったと思います。有名進学校をめざす友人の塾のプリントを見たら、「名詞、動詞、形容詞、形容動詞、副詞・・・」など、国文法用語のオンパレード。「主語、述語」までは授業で習ってなんとなく知っているけれど、「詞」ってなに?という感じでした。
中学1年の国語の授業では「比喩」という用語を書けなくて失点。先生が一度きり黒板に書いて、さっと消した用語で試験され、当時相対評価の中で国語の5を逃して4なんてことがしょっちゅうでした。中学2年になると、小学校のときに??となった「詞」などについて授業で網羅。用語を丸暗記してしまえば、今で言えば「メタ言語」として、勉強の理解を助けてくれる武器と感じるようになり、文法って面白いなと思うようになりました。
普通高校で大学受験のために古典、古文を習います。中学校までは「この」は連体詞なのに、古文では代名詞「こ」と格助詞「の」と覚える(記憶は曖昧)なんてことが起きて、どうして同じ日本語なのに文法用語が違ってくるの?と不思議に思いつつも、受験のためだと辛抱して人並みに勉強していました。
一方英語はどうだったというと、授業で習ったことはそれなりに理解していますが、話せるわけでもなく、いろいろ頑張っても語彙が増えるわけでもない。ゴリゴリのオーディオリンガルな授業、フォーカス・オン・フォームズの世界の中で、いつ英語って話せるようになるものだろうかと絶望していたものです。大学生になって家庭教師で中学生に英語を教えようとすると、This is a pen.のthisは「これ」なのに、This pen is nice.とくるとthisは「この」となり、生徒さんは頭がパニック。英語学習というよりも、日本語の問題じゃないか、と、日本語というものについての興味が少しずつ開花しかけていました。
1浪し、苦心して入学することができた大学では、政治学科で政治学が本分でありながら、第二外国語のスペイン語にどっぷりはまりました。親の仕事の都合で海外経験豊富かつ英語もペラペラの猛者が集う英語の授業に比べて、スペイン語のクラスはほとんどが未経験者。スタート地点が同じなら、1番を取る余地もあるなんて色気を出したのが最初でしたが、やればやるほど楽しくて、「そこまで勉強しなくても単位は取れるでしょ?」と変わったやつだと思われながら、NHKラジオスペイン語講座にまで手をだして独学で勉強していました。スペイン語という言葉は、日本語と同じで母音が多く、概ねローマ字の雰囲気で読めるので発音のコンプレックスがありません。そして、スペイン語のクラスに集う仲間は明るくて陽気で優しい人ばかり。英語だとコミュニカティブな授業みたいなことで、ピア学習とかさせられて、気恥ずかしくてどうにもならないのですが、スペイン語は文型積み上げでコツコツやるだけでも、やればやるほどコミュニケーションできるようになる感覚があったので、なんて楽しいんだと思ったのです。中学高校では友人にからかわれないようにあえて英語の発音を下手にして授業に望む文化であった一方、大学ではネイティブなみのアメリカ式のまろやかな発音、シャープなイギリス式発音が飛び交って、田舎者の私は途方にくれるだけだったのですが、そこに火をつけてくれたのがスペイン語でした。
社会人になり、英語を使って社内文書やプレゼン資料を作らなければならなくなり、とても苦労しました。TOEICは825点までは頑張ったものの、そこから全く伸びなくなりました。ボーナスを手にした時、英語の勉強をしてみようかなと町を見渡すと、さまざまな語学学校があります。しかし、わたしは比較検討の後、夜間の大学に入学することを決意しました。
夜間の大学は、文学部の英米文学科。TOEICの点数で認定の単位を稼いだりしながら、社会人、マダム層、昼働きながら学校に通う若い世代の学生と一緒に学びました。スペイン語を第二外国語でまたまた選択して、ドラクエでいえば序盤でメタルキングの剣を持っているような無双っぷり。一度学んだ言語を最初からやり直すのも楽しいものだと思いました。
英語は結局その後も泣かず飛ばずだったのですが、楽しかったのは英語音声学。パソコンで母音や子音の波長を分析して、いまどこが阻害されたか、なんてやりました。このとき、調音点、調音法という言葉を知り、「破裂音」「摩擦音」「破擦音」・・・と覚え、単位をとって卒業したのでした。
日本語教育能力検定試験の受験を決意
日本語学校(告示校)での仕事に関わり、試験を受ければ日本語教師の資格が取れることを知りました。一般には、大学で専攻したり、副専攻で単位をとって資格を取得するケースがあると聞きました。また、大卒であれば420時間講習を受けて、検定はまだ合格していなくても告示校の日本語教師になれるとのことでした。私は「検定のみ」の選択をして、出願。夏頃出願して、10月に受験したと記憶しています。過去問と、練習問題集、基本書、用語集の徹底回転で、ギリギリ合格できました。
日本語教師デビュー時の苦労の連続
デビューは突然やってきました。この編の経緯はまた別の記事で紹介しようと思います。採用されて入ってくる同僚の先生方は経験者ばかりで、専門用語だけでなく、業界の「略語」を連発。「完マス、ポイプラ」なんていうJLPT(日本語能力試験)対策テキストの略称オンパレードで、おいおい、なんだそれ?とカリキュラムやシラバスの表を見て悩む日々でした。
いざ先生を始めても、とにかくやんちゃな学生揃いて学級崩壊直前。押しても引いても大騒ぎ。ときには持ち前の大きな声で私語をかき消し、異文化ならではのワガママをねじ伏せて、すこし乱雑に授業を進めたものです。思えば1年から2年の間は、日本語の授業というよりは、中学校の体育の先生のように口やかましかったかもしれません。
学生とのコミュニケーションの蓄積がうまく続くようになり、信頼関係ができてくると、ようやく授業らしいことが学生に届くようになりました。夏休み、冬休みなどの長期休暇のたびに、学生たちは日本語力を上げてきます。いわゆるBICS(生活言語能力)をあっという間に高めてくるのです。一方、CALP(認知学習能力)というのは、日本語教育能力検定試験のテキスト通り、身につくまで時間がかかるようで、なかなかテストの点にはつながらないやんちゃボーイズ。日本語学校在籍中最後のJLPTではN3にも数名合格し、卒業。専門学校や大学に進学するの姿を見て、これで日本語教師一周かとため息をつきました。
420時間の養成講座を受けた先生方は、講座の友人とのつながりもあり、模擬授業などで授業のやり方を十分に研究してきています。ところが「検定のみ」「コネ採用」のわたしは、授業のイロハのイも知りませんでいした。「ドーニュー、ドーニュー」と飛び交う言葉に、新しい牛乳か?ギャグにもならないと考えながら、勢いだけで教壇に立ち続けたのでした。
本来は文法理論好きのはずの自分が、日本語学校の現場に出ると、それを一切置き去りに。そしてとにかく45分4コマの授業を成立した格好にし、見よう見まねで授業引き継ぎを書く。なるほど、あの先生はこうやっているのか、という繰り返しの中で、少しずつ授業らしいものができるようになっていったのです。
新制度のもと、日本語教員試験を受験
日本語教育能力検定試験に合格して日本語教師としてデビュー。それで苦労しながらも楽しく授業をしていたのですが、制度が新しくなって日本語教員試験(国家資格)が始まりました。不動産屋など宅地建物取引業者は宅建業免許が必要で、そこで働く人には宅地建物取引士という個人の資格が必要です。これと似たような感覚と私は解釈していますが、日本語教育の新しい制度では認定日本語教育機関で働くには、登録日本語教員でなければならず、登録されるには日本語教員試験合格が必要ということです。何回試験を受けさせるんだよって感じですね。
現職で1年以上勤務経験が証明されれば、移行措置として日本語教育能力検定に合格している教師ならば日本語教員試験の基礎試験と応用試験が免除されます。しかし、免除申請すると講習というものを結構たかいお金を出して受講しなければならない。
日本語教員試験という新しい試験を始めるからには、この新しい試験に対して学び直すことが、国が求めている日本語教師のアップデートだ!なんてイキったことを考えてしまい、免除申請しないで「基礎試験」と「応用試験」をうけたろやないか!となりました。いわゆる「Fルート」受験です。それで、この記事を書いている2024年11月上旬現在は、2週間後に迫る第一回の日本語教員試験対策で再び試験勉強に漬かる日々です。
まとめ
私の半生の中で、どのように言語に関わって、どのように日本語教師という仕事に着地したかをまとめました。まだまだ大した経験はありません。しかし、言語、言語教育には相変わらず興味は深く、これからも益々学んでいきたいと思っています。
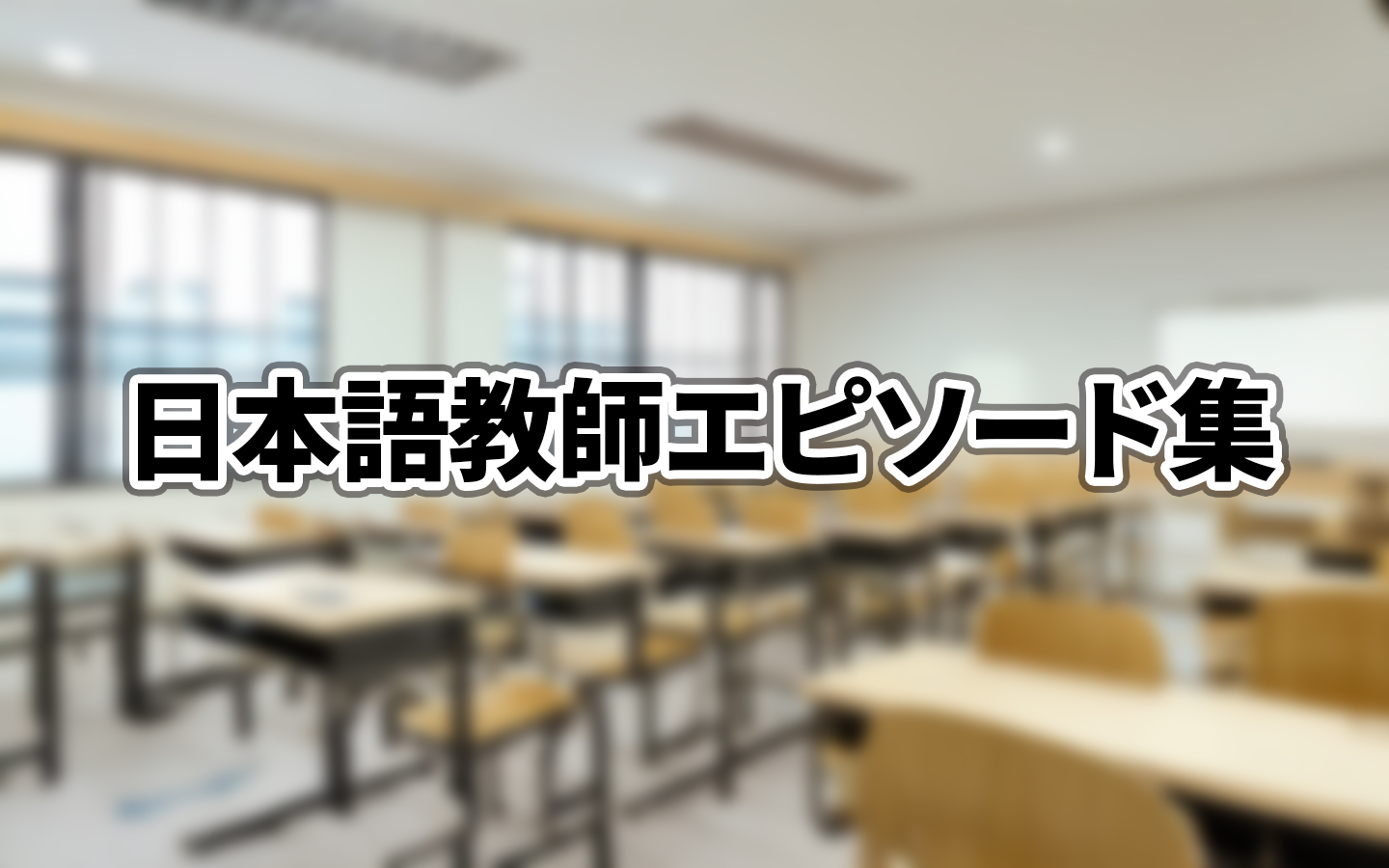


コメント