この記事は、日本語教育・日本語教育業界・日本語教師がおかれる昨今の状況において、問題や課題になっていることを「日本語教師個人」の視点で見つめていくことにより、「自分は関係ないからいいや」というスタンスから、「自分の悩みやニーズの共有が他の日本語教師の助けになり」、ひいては日本語教育業界が活性化することにつながることを信じて、私が思うところを述べるものです。
政治家に相談した答えが「コレジャナカッタ」話
私がある政治家(地方議員)の「代書」の仕事を請け負っていたときの話です。選挙のときでした。ある市民がその政治家のところにやってきて相談しました。「不景気でどうしてもいい仕事に就けない。なんとかならないか。」その政治家は「わかりました。頑張ります。でも、選挙に通らないと何もならないから、協力してください。頼んます。」となりました。市民は一生懸命その候補を応援し、晴れて再選しました。
しばらくしてその市民が、その政治家を再び訪ねました。「まえにお願いした仕事の件、どうでしょうか?」と催促しました。すると、その政治家の答えはこうでした。「おー、私もかなり頑張ったんですよ。昨年の失業率がね、4%が3%に下がったんですよ(数字は例として、架空)」。質問した方は顎がポカーンとなった表情で帰っていき、二度と顔を見せることはありませんでした。
政治家の視点と、市民の視点は違って当然だったという話
私はこの市民の相談する姿と、答えをもらう姿をたまたま両方目撃しました。そうか、政治家というものは市民みんなのために働く存在であって、個別になにかを解決するための存在ではないのだろうなと思いました。法律的なトラブルや、行政手続き上の困り事で政治家に相談する市民もたまにいます。市役所や都道府県に「口利き」をして、うまくことを進めたという話もよくききます。しかし、本来「政治家の口利き」というのは変な話であって、法律問題や行政手続きの問題は、弁護士・司法書士・行政書士などに、業務内容に応じて相談し報酬を払って解決してもらうべきものなのでしょう。
「自分の仕事のことで相談したのに、県の失業率が改善したという答え」が返ってきたというのは、ある意味まっとうな政治家なのかもしれません。市民とは全体の市民のことであって、この相談者個人のことではなかったのですね。
この経験を通して私は、問題や課題を解決するには、①政治家・経営者的のような「政策的な視点」と、②自分のこととしての「個人的な視点」をバランスよく切り替えていかなければいけないと思うようになりました。2つの視点は両極的なもので、同時にあっていいものです。しかし、あまりにマクロに、つまり大局的な話をしすぎると、②の答えがいますぐ欲しい個人からすると、自分は関係ないからもう関わるのやめとこ、となってしまうのです。
日本語教師の悩みを整理する視点
どんな仕事も大変なものです。だからもちろん、日本語教師という仕事も大変です。日々悩みます。小さな悩み、大きな悩み、いろいろあります。解決できることばかりではありません。ましてや教える相手が異文化出身の外国人留学生。うまくいかないことがあって当然です。先生と先生の間も、人間同士のことですから、仕事の仕方が合わないなど、いろいろな問題があるものです。
私は大変な仕事を担当している。だからといって私の悩みが日本語教育の世界での普遍的な悩みかというと、すぐツッコミが入るでしょう。「そんなの、こうやって解決したらいいじゃん。」と。どうして悩んでいるか、どういう背景があるのかという文脈まで伝えて相談するのは大変ですから、誰かに相談しても政治家に相談したのと同じような「コレジャナカッタ」感にさいなまれ、もう誰にも言わんとこ、となってしまいがちなのです。知らんけど。
10年後の日本語教育にビジョンを持って課題を解決していくのは文科省の仕事であって、学校の経営者にお任せしたいことです。日本語教師個人は責任とれません。それよりも、まず明日の授業をどうするか、残業減らすにはどうするか、効率的に仕事をまわして現場の先生が幸せになるにはどうすればいいかという考え方が、とても重要ではないでしょうか。
小さなことからコツコツと、チリも積もればマウンテン
「小さなことからコツコツと」といえば、西川きよし師匠です。「チリも積もればマウンテン(山となる)」は、こち亀の両津勘吉からの引用です。これしかありません。小さくて、チリのような小さな悩みをコツコツと解決して、解決事例を積み上げることが、明日、明後日の自分を幸せにすることにつながるのではないでしょうか。
いつか解決事例の積み上げ、文字通り「積分」されたときに、経営者、文科省、政治家が大きな視点から現状を改善するために、大きな流れを変えていく判断材料にしてくれるかもしれません。
事件に大きいも小さいもない。事件は事件。
これは踊る大捜査線の恩田すみれ(深津絵里)のセリフですね。どんなに小さな悩み、課題、ニーズも、解決すれば必ず次に繋がるものです。逆にほうっておくといつまでも改善されず、永遠に悩み続けることになります。悩みを共有することは一時の恥、として気軽に相談できる仲間がいればいいですが、より具体的な解決を得られる共有相手が広がれいいですよね。
誰かに相談して、解決策を摸索するという態度でいえば、私の勤務校のネパール人学生はなかなかたくましいです。なんとかして答えがほしい。先生も一人だけ相談するのではなくて、あちこちに相談する。本当、何度もいいたくなるほどたくましいんです。見習っていいなと思う姿勢です。
マクロに、巨視的に、抽象的に問題を分析することも大切なことなのですが、とにかく目の前の課題を解決する方法を見つける。今はググればすむことも、AIに聞けばすむことも多くなりました。しかし、どこまでいってもこの仕事は人間がやっていることなので、最後は誰か同じ立場で経験豊かなに人に相談するしかありません。
まとめ
「留学生を支援するイベント」という企画をもってきてくださる企業があります。大変素晴らしいことです。留学生が交流して、いい就職先をみつけて、地域経済に貢献する。企業だけでなく、公的機関もさまざまな留学生支援を行っているようです。しかし、これが日本語学校の日本語教師にはまったく響かない。当然です。関係ないから。日本語教師も教える機関で立場は様々ですが、私のような告示校の日本語教師という、留学生の最初の入口の学校で働いている者からすれば、留学生を専門学校や大学に上げてしまえばそれで仕事はコンプリートです。就職するころになると、もう新しい世界で学生たちは頑張っているので、日本語学校に来てまで就職の相談に来たりはしません。関係ないからこそ、「留学生支援の取り組み」が、日本語教師個人に響かないのです。
日本語学校の日本語教師、専門学校・大学・短大という上級学校の日本語教師がバラバラのままでいいとは思いません。日本語教育参照枠ができて、留学生の学習の評価をさまざまな段階でわかりやすくしていこうという方向になっています。日本語教師である以上、就職先としてそれぞれが選択肢になるので、できれば業界全体が協力しあっているのが理想でしょう。
「留学生を支援する仕組み」が、もちろん第一義的には留学生のためのものであったとしても、日本語教師個人、日本語教師にこれからなろうと考えている人、そして外国人と共生していくために日本語教育が必要な企業、家庭の人にとっても、これは他人事ではなくて自分事だと刺さるような、個別具体的な解決事例の蓄積があると、より多くの人が巻き込まれていって、盛り上がるのではないかと思います。
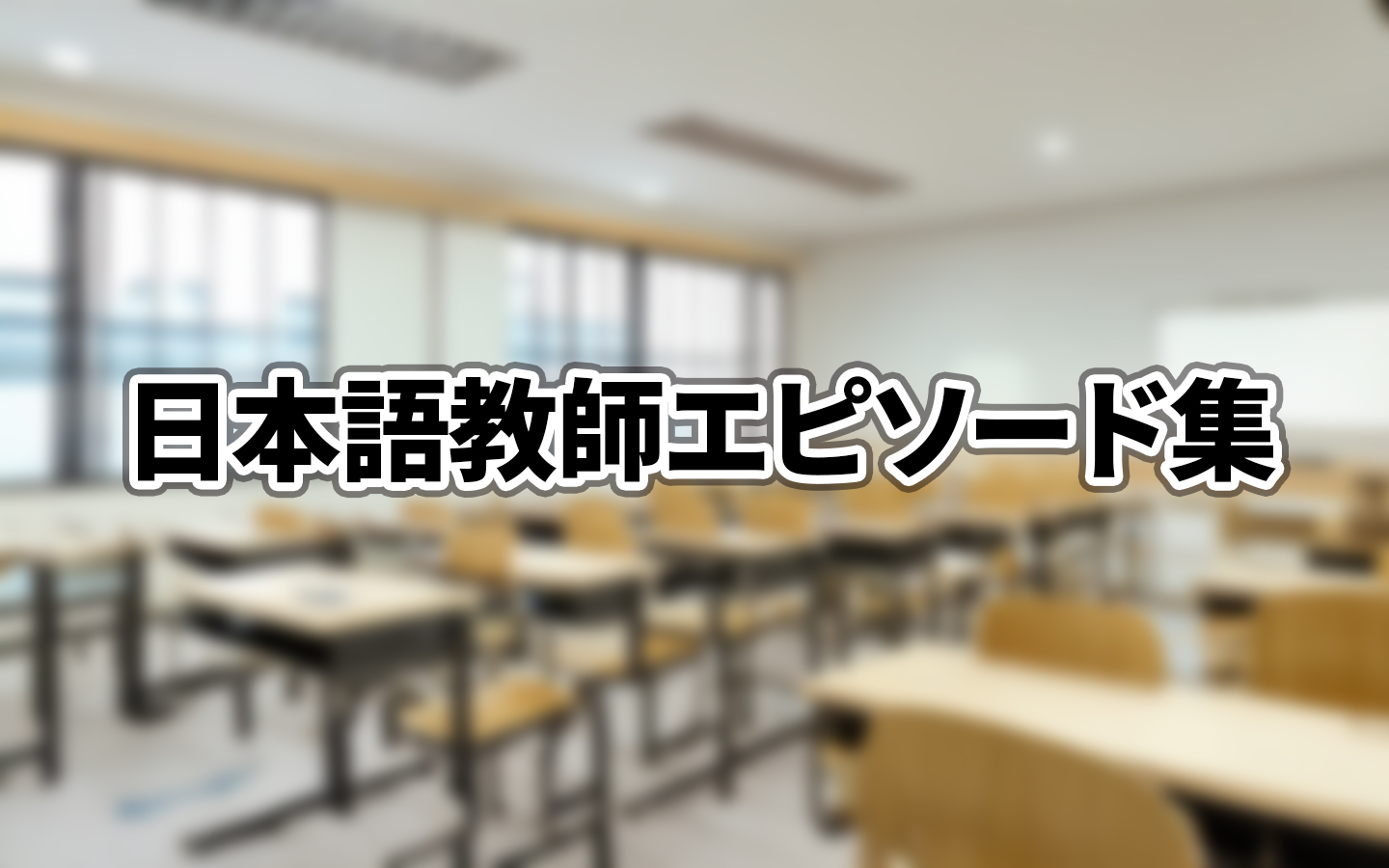

コメント