この記事は、日本語教師が巻き込まれる可能性がある「危機」について考えていくものです。
一言で言うと
一般企業と同じく、日本語教師にも『危機管理』が必要。危機への備え、対応経験をスキルに変えていきたい。
「危機」の主体
- 日本語学校の危機
- 日本語教師の危機
- 日本語学校の留学生の危機
という見方になります。
第一に、学校という組織のには、経営難や不祥事など様々な要因での危険(リスク)があり、危機は絶対に怒らないということはありません。しかし、今回は日本語教師個人の視点によるお話なので、経営者目線の議論は割愛します。
第二に、日本語教師の危機といえば、職を失わないかということよりも前に、時として「命」に関わる危機もありえます。私が人生で初めて命の危険を感じた事件について、回想していきます。
第三に、学生が巻き込まれる事件、事故、被害または、加害者の方になってしまう可能性という文脈での危機です。
日本語学校の危機
まずは、経営が危なくなるという「経営危機」があるでしょう。売上が減少したり、放漫経営でお金を使いすぎるとそうなります。
また、どこかの日本語学校でありましたが、外国人留学生を鎖に繋いだなんていうように、事件として報道されてしまうと、認可を取り消されるところまでいってしまいます。危機どころか、吹き飛んでしまうということですね。何がきっかけで「炎上」して、学校の経営が危うくなるかは完全に予測できません。
日本語教師の危機
先生の危機といえば、職を失うということがまずあります。しかし他にも、トラブルで「命や健康」を失う危機もありえます。私は、自分の教え子の女子学生が同じ国の出身の社会人彼氏のDVにあい、病医院に連れて行こうとしたところでこの彼氏に暴行・傷害を受けるということがありました。命の危険を初めて感じた時でした。警察、検察、入管、各役所と掛け合って、この犯人をなんとか駆逐できましたが、日本語教師の仕事にはこういう危険もあるということを意識しておかなければならないと勉強しました。
学生の危機
学生が加害者になることもあれば、被害者になることもあります。命や健康の危機もあれば、お金の危機、そして信用の危機もあります。一見「喧嘩」で片付けられた騒動も、見方によっては「強盗」ともいえ、脅かされてお金を取られそうになったという学生が私の教え子にいます。
日本語学校の学生はほとんど成年で、責任能力があります。所属の学校の責任ではないかもしれないトラブルでも、ここが火種となって学校の危機につながる可能性があるので、知らん顔はできないのです。
「危機管理」とは、平時から心に地獄図を描くこと
「危機管理」という言葉を作った佐々淳行氏の言葉を借りると、「平時はもうコップに半分しかない、有事はまだコップに半分も水があると思え。」という言葉が危機対処の思想としてとても参考になります。普段から悲観的にとらえて、いざというときには意図的楽観論で臨むというものです。
また「心に地獄図を描け」という言葉も佐々氏は言います。何がよくないことが発生したとき、最悪どうなるかというところまで想定すれば、ああこれくらいで済んだなということになります。
そんな縁起の悪いことを言ってはいけない、考えてはいけないというのが、日本人の悪い癖なんだそうです。「言霊信仰」といいますが、不吉な言葉は言わないようにしたいものです。しかし、兆候はあるのに知らないふり見ないふりをして「想定外だった」と言い訳するのは、人々を幸せにしません。
まとめ
日本の生活に慣れてきた段階の学生は、何を注意しても「だいじょうぶ、センセイ」とおちゃらけることがあります。多少悪いことをやっても、バレなければ大丈夫と。
大丈夫じゃないんです。日本語の構造と同じように、日本ではあとからあとからルールが増えていきます。昔大丈夫だったから、これからも大丈夫ということはありません。危機管理は、最悪を想定して動くということが、個人としても組織としてもとても重要なことなのではないでしょうか。
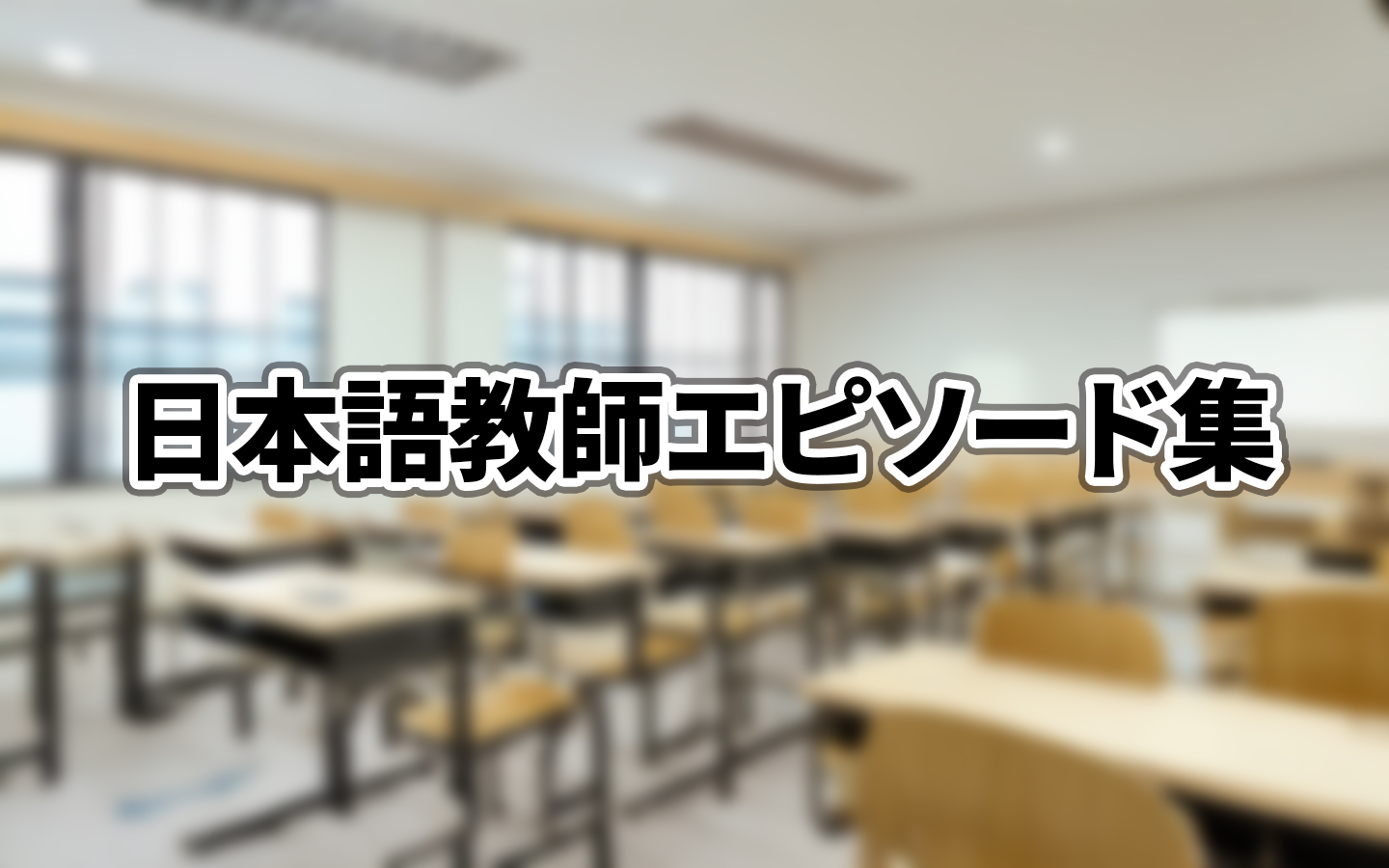


コメント