この記事では、私の勤務校の同僚について書きます。
一言で言うと
残業ゼロのまま、授業バリバリ、進路指導業務もバリバリ、長期休暇は海外旅行行きまくり、実績を積み上げながら日本語教師としての人気とスキルを爆上げしている専任教師が存在している。
真似して仕事したいが、どうやったら真似できるのか問題
ホワイトな職場というのは、トップダウンでそうなるのか、ボトムアップでそうしていくものなのか、なんて考えています。制度として、就業時間できっちり帰りなさい、と上から指示は出ても、仕事は山盛りなのにどうするの?となるわけです。役所でも銀行でも、照明や暖房が切られた暗くて寒い部屋でこっそり仕事しているなんて話を聞きます。どちらからというものではなく、どちらとも必要なアプローチなのでしょう。
やるべき仕事を、時間内に終えるには、何をするべきかを明らかにして、どれくらいの時間をかけてやるかという見積もりが明確でなければいけません。あれもやってみたい、これもやってみたいと考えると、あっという間に時間を食われて、先にやるべきことを後回しにして大惨事、ということになってしまいます。
かといって、今回のエピソードの主役の先生は、あれはしない、これはしないという「仕事の引き算」タイプの先生ではありません。すっと私のデスクにやってきて、「〜ということやってみたいんですけど、どうでしょう?」相談してくれます。私は即いいね!となって、企画を立てて、サポートします。全体会議でもグイグイとみんなを引っ張り、企画を次々に実現。若いんですけどね、その仕事力はどこで身につけたの?と尊敬してしまいます。
コンピュータがめちゃ強いかというと、当初はそうでもなかったと思います。ある日、自分用にPCを買いたいと言い出して、即決でMicrosoft のサーフィスを購入。自宅に仕事を持ち帰っている様子もなく、デスクに置いたままなのですが、毎日コツコツとExcelなんかの関数を覚えていって、今はなんでもできるようになりました。
私は何かを覚えようと思う時は、完全に「文型シラバス」から入ってしまうタイプです。テキストを買って、目次をみながら、必要か必要でないかを考えず網羅的に知識を入れたくなる。そういう勉強の仕方をしてきたから、凝り固まってしまっているんですね。
彼女は対照的で、必要なときに必要な知識をぐっと学んで即実践。それを積み上げていくので、いまどきの若い人が好む「タイパ(タイムパフォーマンス)」がとても高いのです。この芸風は真似したいと思ってもなかなかできない。でも、このあり方こそが新しい働き方のプロトタイプ(原型)なのではないかと思うのです。
真似したいが、どう真似するか、ここが「新しい働き方」を考えていくスタート地点ですね。
まとめ
私の勤務校はこの先生が率先して今どき、そしてこれからの社会でこうあるべきだという見本を見せてくれています。残業して日付が変わるまで学校にいるのが正義ではない!ということを、実証しています。経営者側も大変評価していることでしょう。私はこの先生にくれべれば年嵩を増してしまっていますが、うまい仕事の仕方を分析して、全体に広がっていくような仕組みづくりに尽力したいと思っています。
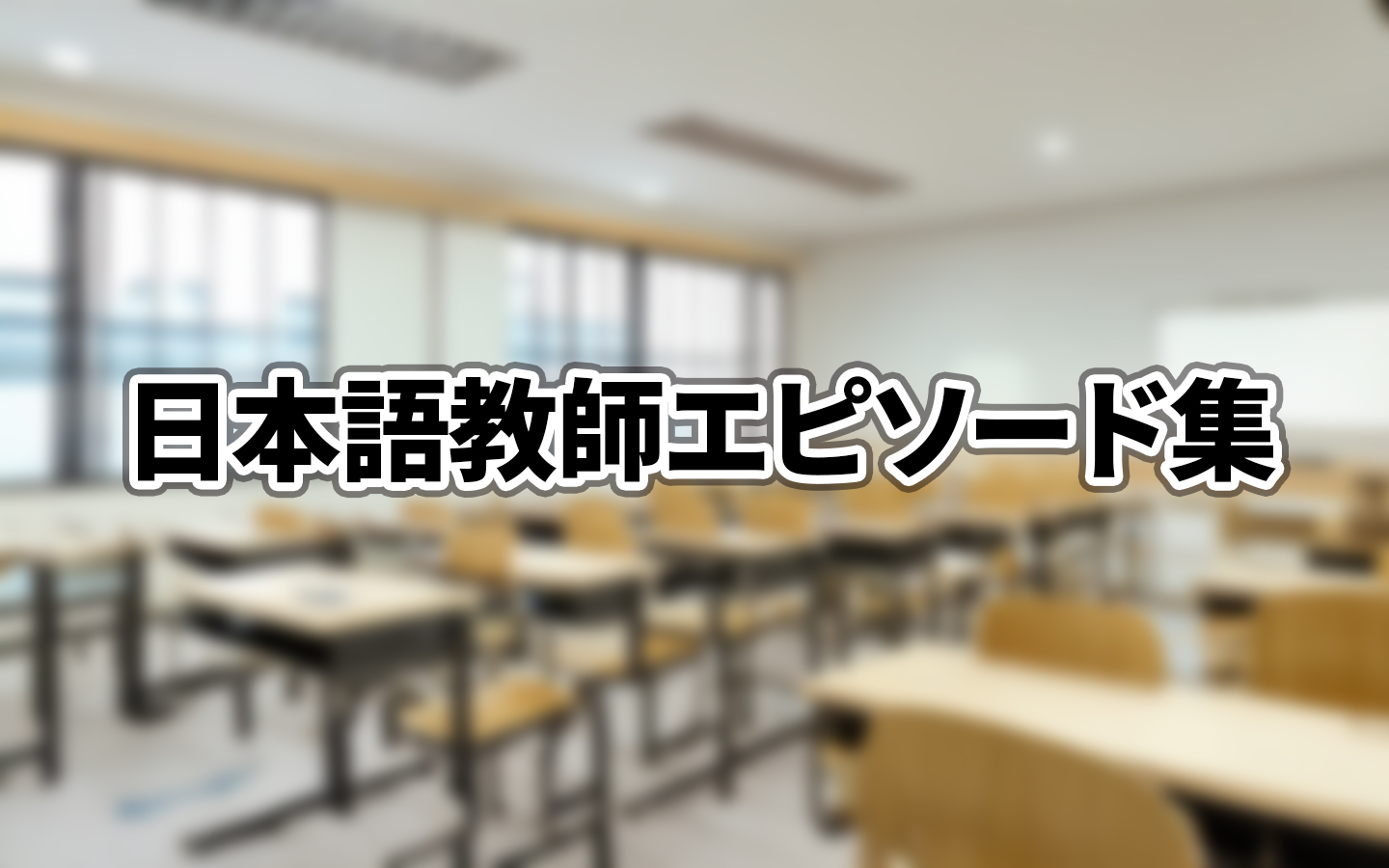


コメント