この記事では、プログラミングを日本語教師や日本語学校の仕事でどう生かせるかについて考えた記事です。
一言で言えば
Youtubeのチュートリアル動画や、AI(人工知能)のお陰で、プログラミングの学習コストやハードルは下がっている。小さなことからでも、めんどうな仕事はプログラミングで片付けれた方が、絶対に幸せになれる。
どこからが「IT化」なのか、「DX化」とは何か
日本語学校は、監督官庁に報告する書類がたくさんあります。最終的にはExcelに入力して提出したり、システム画面から入力して送信したりなど、IT化が進んでいるように見えます。しかし、現場の日本語教師の作業レベルでいえば、「IT化」されているというのは本当でしょうか。
コンピュータで仕事をすることを「IT化」と言ってしまいがちですが、この言葉の使い方は果たして適当なのでしょうか。Information TechnologyがITです。情報技術、うーん。WordやExcelで仕事をすることはITでしょうか。コンピュータ=ITと考えるならば、まちがってはいないような気がします。
最近では「ICT」と言ったりします。CはCommunicationです。LINEやSlack、ZoomといったコミュニケーションツールはまさにICTという感じがします。TeamsやGoogle Classも、みんなでわさわさと情報交換をしていますから、コミュニケーションツールですね。スマホとコンピュータの垣根もだいぶなくなって、コロナ禍前と比べるとICTはかなり進化したと思います。
紙とペンで仕事をすることと、WordやExcelで仕事をすることは何が違うのでしょうか。紙でも、最近ではスキャンしてPDFやJPGにすれば、ICTで瞬時に送信することができます。データで保存すれば、紙は捨てて、スペースを省くこともできます。WordやExcelを使う利点は、コピーして使い回せるというところでしょうか。
Excelの表をコピーして使いまわしていると、書式や設定が少しずつ書き加えられ、最初のバージョンと形が異なってくることがあります。ファイルが100個くらいになったところで、表の形式を統一しようと思うと、ああ困ったとなります。そこで、次の段階で登場するのがデータベースソフトです。
データベースソフトといえば、ちょっと昔の人から聞くと「桐」というソフトがあったそうです。マニアックな感じがしますが、当時は使いやすかったとききます。Microsoftで言えば「Access」です。私も使ったことはありますが、正直マスターできませんでした。15年くらい前は、今のようなYoutubeでチュートリアルを見て学ぶということはできないので、本を読んで学ぶしかありません。Accessは、独学では少々厳しいソフトだなぁと、今も思っています。
iPadが登場してから一気に伸びた気がするのが「FileMaker」です。Appleの子会社ということで、iPhoneやiPadなどのiOS機器との親和性で爆発的に普及した感じがします。今はClaris FileMakerと、会社の名前もすこし変わっています。私は「FileMaker」でのスキル、経験は中級+αと自己評価しています。データベースとレイアウト画面をうまくスクリプトで制御して、帳票などをPDFに大量・高速・正確に出力できます。しかも、ローコード(プログラムを書く負担が少ない)で。
FileMakerをいじって、簡単な業務アプリみたいなものを作っていくと、今度は本格的なプログラミンでいろいろやりたくなります。Python、Javascriptなどのプログラミング言語を覚えると、コンピュータに仕事をどんどん任せることができるようになります。プログラミングは基礎からコツコツ学ぶことも重要ですが、ChatGPTに「〜のためのプログラムを書いて」と依頼すれば、たいていのことは教えてくれるので、初心者でもなんとかなります。
私は、仕事は結果が出れば手段は何でもいいものだ、と「本来は」考えています。スタートからゴールまで一直線に考えるタイプの人は、今回はこれでいい、とりあえずこれでいいと、姑息的(ずるいという意味ではなく、医者が使う意味)な手段を好むでしょう。
しかし、同じような仕事がまたいつかやってくるときは、使い捨てのような仕事の仕方よりも、次回使い回せるものを残しておいた方が有利です。毎回最初からやる必要がないですからね。そして、繰り返したり、条件によって処理を分岐したりする場合は、プログラミングを活用した方が圧倒的に速いわけです。
コンピュータを使っても、紙でやっているのと変わらない仕事の仕方もあります。印刷を前提にした妙なExcelの使い方を「神(紙)Excel」と言ったりします。申請書などの様式がせっかくExcelなのに、男・女や、有・無の選択欄が図形の◯で選ばなくてはならず、結局印刷前提だからプログラミングで集計できないという話は枚挙に暇がありません。かといって、完全にオンラインのフォームにできるかというと、また別の問題がでてきますが、この辺はまた別の機会に。
大きな流れで言うと、紙で済ませられる段階(フェーズ1)と、Excelなどのファイルでやる段階(フェイーズ2)と、データベース化してプログラミングで処理するという段階(フェーズ3)が考えられます。流石に今どきはフェーズ2でやっている学校、会社が多いとは思うのですが、時々超アナログなフェーズ1オンリーのところもあるようです。これは、それぞれの組織の仕事の内容によるものですから、どれかが正義というものではないですね。
さて、フェーズ2からフェーズ3に移りたいと思っても、このハードルが現実的には高いのです。なかなか「データベース」の考え方で次の段階に移行できない。というのは、Excelを使っているが、データベースとして使っているのではなくて、紙の表と同じように使っているから、という原因があります。
「データベースファースト」という考え方ありますが、これを外すとせっかくのExcelが、今回限りで賞味期限が短いデータになってしまいます。フェーズ3に行くためには、これは絶対に学ぶべきところですね。そして、もう一つ乗り越えなければならないのは、「リレーショナル・データベース」の概念。これは、わかったようで、わからない。腑に落ちるまでに私は20年の月日が過ぎていました。
私は、仕事でプログラミングをどんどん活用しているので、「プログラマー」であると思っています。しかし、なんとかエンジニアみたいなプロフェッショナルではありません。必要なときに必要なプログラミングをみつけてきて、そこそこに使う。日本語教育の世界の言葉で言えば、「行動中心アプローチ」で、自分に必要な「Can-doリスト」を少しずつ増やしているだけです。「文系プログラマー」という表現もあるようですが、適切かどうかはわかりません。まあ、便利なものは使えばいいじゃんプログラマーであるということでご理解ください。
ここまで書いて、やっと「DX」の話ができます。最近の専門学校には「DXビジネス学科」のようなところが増えました。コンピュータをビジネスにうまいこと使うという意味ですね。留学生は在留資格(ビザ)が欲しいので、就職してからもビザを得られるような学校に進学しなければなりません。
経営経理会計などは、就職する際にわかりやすい学科です。観光ビジネス、通訳もわかりやすいです。しかし、エンタメ業界なんかはなかなかビザがとれるか不安ということもあり、ネパールの学生なんかには人気がありません。エンタメもビジネスですから、可能性はある思うのですが、まだ実例が少ないせいか、参考になる先輩がいないようですね。
DXを学べば、就職に困らないというのは、確かにそうかもしれません。大抵の企業、サービスにはタッチパネルの機器があって、大量のデータを処理し、活用してビジネスをしていますね。現実は仕事の現場でタッチパネルを押すだけであっても、DXはDX。うーん、DXって本当はどういうことなんだろと悩みながらも、DX系の専門学校は人気が高まっているので、どんどん送り出さざるを得ません。
まとめ
コンピュータ化、IT化、ICT化、DX化という言葉は、定義がいろいろあって、厳密に知って使うと、業務改善につなげていく基礎になります。そしてコンピュータで情報処理といっても、実質アナログなフェーズ1、プログラミングを使って処理するようなフェーズ2、DXで完全自動化というようなフェーズ3があります。
日本語学校においては、完全自動化フェーズ3の段階がやってくる日はまだまだかなと思いますが、フェーズ1の仕事をフェーズ2にもっていくだけでも、面倒な仕事にかける時間を削減することができるでしょう。
今回は概念的、抽象的な話に終始してしまったので、次の機会では超具体的な事例をまとめていきたいところですが、結論は頭書のように、「手間のかかる仕事は、プログラミングで片付けてしまえばいい」とうことです。
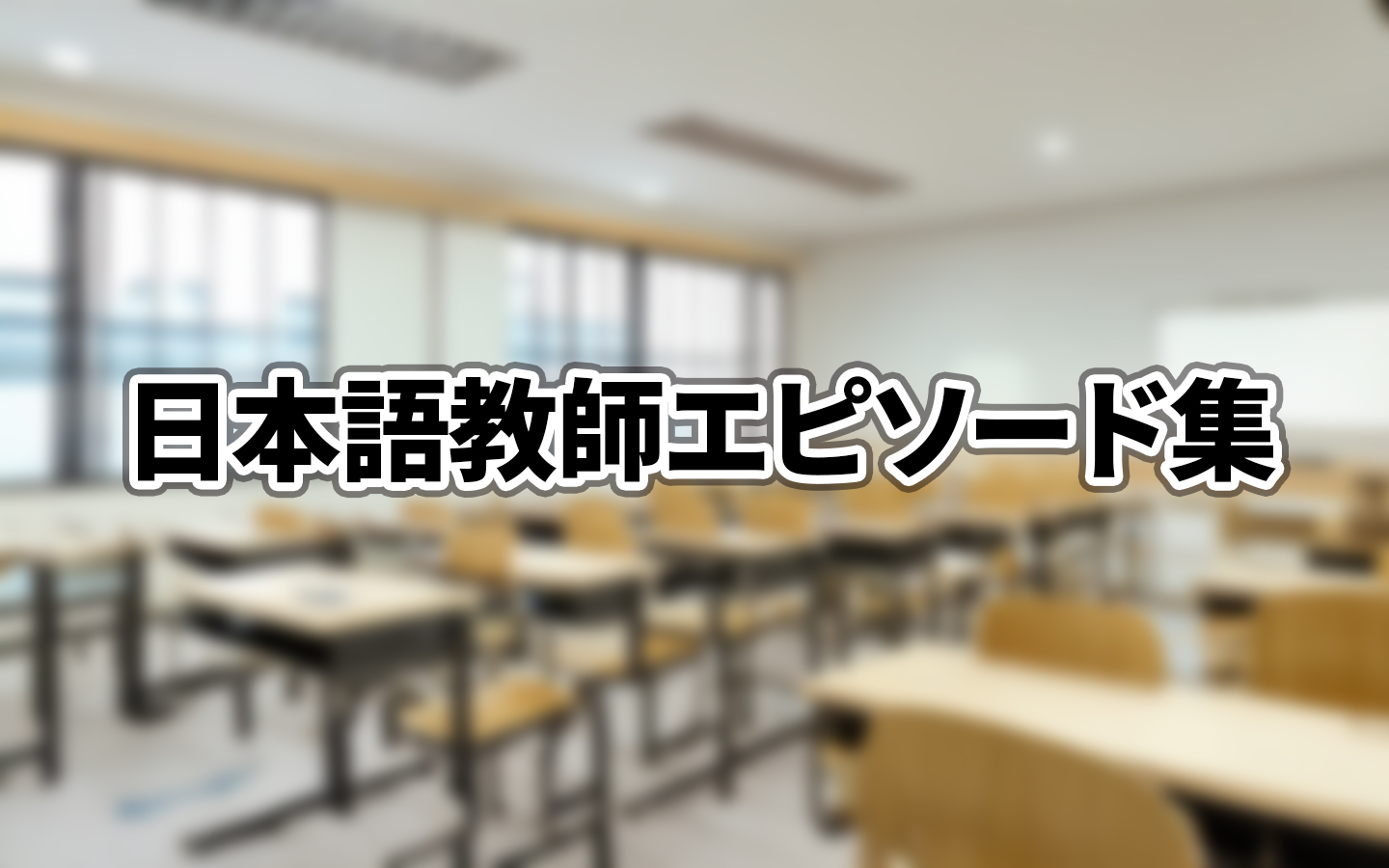

-120x68.jpg)
コメント