この記事は、日本語教師という職業について、3つのアスペクト(局面)でどのような苦労があるかについて述べています。
一言で
日本語教師という職業はやり甲斐もあって楽しい仕事だが、①なるのが大変、②はじめるのが大変、③続けるのが大変、というそれぞれの局面で苦労することが多い。
①日本語教師になるが大変
「日本語なんて、日本人なんだから誰でも教えられるっしょ」、これが日本語教師が周囲の人から食らう、あるあるの言葉です。日本語話せるから営業成績トップになれるかというとそういうもんでもないので、日本語教師として必要な知識、技能、態度というものがあります。
資格が必要か?というと、自分でみつけたお客様に日本語を教えるのであれば、塾の先生のように特段資格が必要ではありません。しかし、知識や経験に乏しくて、教える技能も低かったらお客様がつかないので当然苦労することでしょう。
日本語学校のカテゴリに「告示校」というものがあります。法務省の告示基準を満たしている学校という意味で、要するに国の認可がある学校という言い方で問題ないでしょう。このような学校で働く場合には、例えば日本語教育能力検定試験に合格している、などの要件があります。ご存知出ない方は、「日本語教師 告示校 資格」と検索してみえてください。
養成講座通称「420時間講習」を受講したり、日本語教育能力検定試験に合格したり、大学や大学院で単位を取った、などの様々なパターンから日本語の先生としての資格を得ることができたのですが2024年の法律施行で、国家資格としての日本語教員の資格制度が創設されました。
現職の先生の移行措置が5年間あるものの、これから新しく認定される日本語教育機関で働くためには「登録日本語教員」でなければならいということになっています。登録日本語教員になるためには、2024年に初めて行われる「日本語教員試験」に合格しなければなりません。これまで養成講座や検定試験にお金を使ってきたのに、またお金とるのかよってなもんで、制度が変わるといろいろなお金を取られて現職の先生も大変です。これから先生を目指す人も、コストをよくよく計算しないと、将来取り戻せるのかという不安になってしまいますね。これが、①なるのも大変問題です。
②日本語教師を始めるのが大変
この局面も、細かく言えば就職先を探すのが大変という意味と、就職したはいいものの、教壇にたっていざ始めるぞというときに経験する苦労などに分かれます。
日本語学校をはじめ、日本語教育機関の数は、一般の企業に比べると数が多くはないです。どこに住んでいるかで、通勤の事情も異なります。働きやすいと評判の学校があっても、九州から北海道に通うわけにはいきませんし、地方によっては1つ2つで、募集がなかなかないということもあります。頻繁に募集し続けている学校は・・・、なんていう想像もしてしまいますし、自分が思ったような学校に就職することは「縁だのみ」かもしれません。
日本語教師として就職し、いざデビュー!となっても、新任だと何をどうすればいいの?と悩むことがあるはずです。手取り足取り、OJTで指導してくれればいいのですが、あたな日本語教師の資格あるんでしょ?知っててあたりまですよ!なんて言われたら、もう主任先生や先輩先生に質問することも萎縮してしまいます。職場の雰囲気という意味でも、先生を始めるときは大変なことがあるなぁと思います。
③続けるのが大変
日本語教師という仕事は、留学生という人間相手の仕事ですから、仕事をつくると際限がありません。しかし、学校としての売上=学費は、定員いっぱいまでしかいただけるものではないので、売れば売るほど儲かる商売ではありません。だから、会計上コストとなる仕事はやりすぎてはいけないという方向性になっていきます。
新しい学校が始まったときは、手探りです。あれこれ学生のためにやってみようとサービス精神旺盛に頑張るのですが、そうすると先生の負担になりすぎてしまって、いい働き方を維持できなくなります。先生が辞めてしまうと、他の先生の仕事が増えて悪循環。誰かが犠牲になって支えているというようなケースもあるのでしょうが、あるべき姿とはいえません。
経営者や校長、教務主任というようなマネジメントの立場にある方々は大変です。経営を安定的に維持しなければいけない一方、監督官庁からの厳しいチェックもしっかりうけて、なおかつ学習実績、進路実績を出し続けなければなりません。これはもはや解のない方程式のようなもので、ある程度どこかを妥協しなければ先に進まないというのも現実なのではないでしょうか。
「事務や進路指導が忙しくて授業準備ができない」という悩みは、日本語教師の普遍的な悩みではないでしょうか。本来日本語を扱うのが仕事である「日本語屋さん」が、新しい日本語の仕入れをできないまま、古い商品だけを売り続けるのは楽しくありません。生活指導や、学生のトラブル解決に時間をとられていて、授業があまり締まらない感じにあり、学生の学習意欲が低下するなんてことになると本末転倒ですよね。
まとめ
日本語教師に①なる、②はじめる、③続ける、という局面で遭遇する苦労について書きました。これに対する解決方は、それぞれの局面で各個人が解決法を摸索していかなければなりません。学校の経営者やマネジメントの方々は、ただでさえ解けない方程式に日々苦労しているので、改善策が上から降ってくるの待っても、自分の悩みや苦労の解決、ニーズを良い方向に変えていくことは難しいでしょう。
小さなことから、まず自分のことについて、いかにうまく仕事をしてくか、ということを考えていかなければいけないと思います。
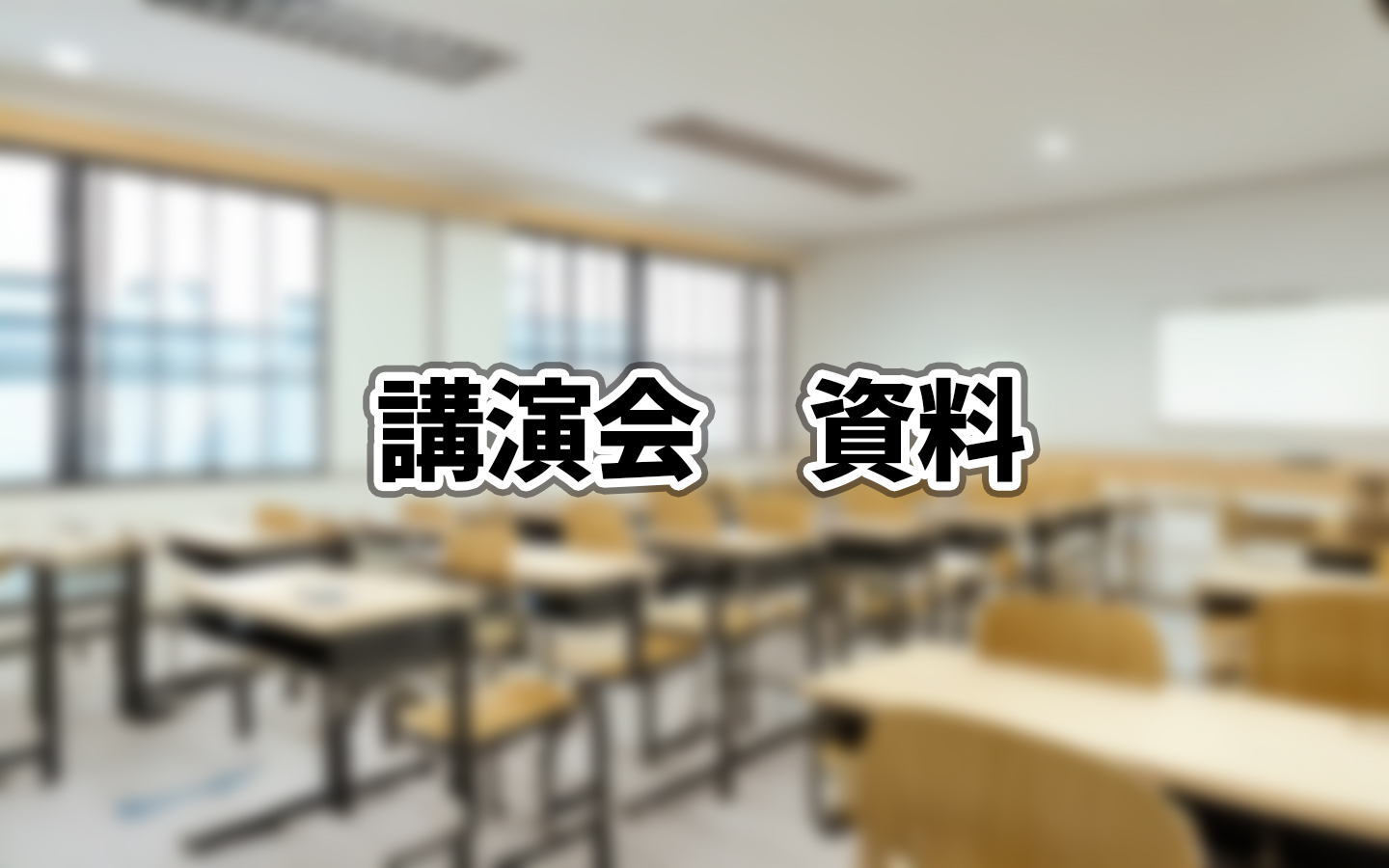

コメント