この記事は、私が新任日本語教師の頃に、ベテラン教師の先生方た使う略語に驚いてしまったというエピソードです。
一言で言うと
日本語教育の現場では、職業語、隠語というほどの特殊性はないにしても、共通理解を前提した「略語」が存在する。
カリキュラムの「略語」が難しい
「みん日」、「でき日」、「ポイプラ」「完マス」などなど、初めて聞いたときは、なにそれ?という略語に多く出会いました。なるほど、「みんなの日本語」、「できる日本語」、「ポイントアンドプラクティス」、「新完全マスター」など、定番のテキストには現場の先生が呼称に使う略語が存在するのですね。
「プレスメ」もびっくりしました。「プレイスメントテスト」、つまりクラス編成のための実力測定テストですね。「プレメン」じゃないのかとも思いましたが、マクドナルドの「マック」、「マクド」問題のように、地方差もあるかもしれません。
カリキュラム表、シラバス表、引き継ぎシートなども略語が踊りくります。「FB」、フィードバックも、一瞬考えれば文脈から理解できるのですが、一通り理解するまで苦労したものです。転職したときに、新しい会
社の用語にとまどうことがありますが、日本語教育の世界でもこういうことがあるんですね。
聞くは一時の恥、だが
聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥です。素直に聞けば済む話なのですが、聞いてしまうと「え、そんなことも知らないの?」とマウント取られるのが嫌だ!と思ってしまうと苦労します。日本語教師は元来、相手が理解しているかどうかに敏感な職業なのですが、「これくらいは知ってますよね?」と、既習語みなしで厳しくしてしまうときもないとはいえないもので、新任の先生には語彙リストとして提示してあげたほうがいいかもしれません。
だんだんと校内ドキュメントが改善され、略語を使うときには文書の冒頭で示されるようになりました。プログラミングでいえば、冒頭でしっかりと変数を定義・宣言するようなものです。定義されていない変数を使うとエラーになっちゃうのは人間も同じですからね。
まとめ
どんな小さなことでも質問されたら「これはこういうことですよ」と何度でも教えるか、「そんなことも知らないの?」と突っぱねるか。文脈も事情もあって、一般化しては言えないのですが、私は何度でもしつこく説明するを苦としないので、芸風としては前者です。一回目の説明よりも、二回目の説明の方が上手になってます。聞いてくれたら、私の利益、みたいな感じでやっていきたいですね。
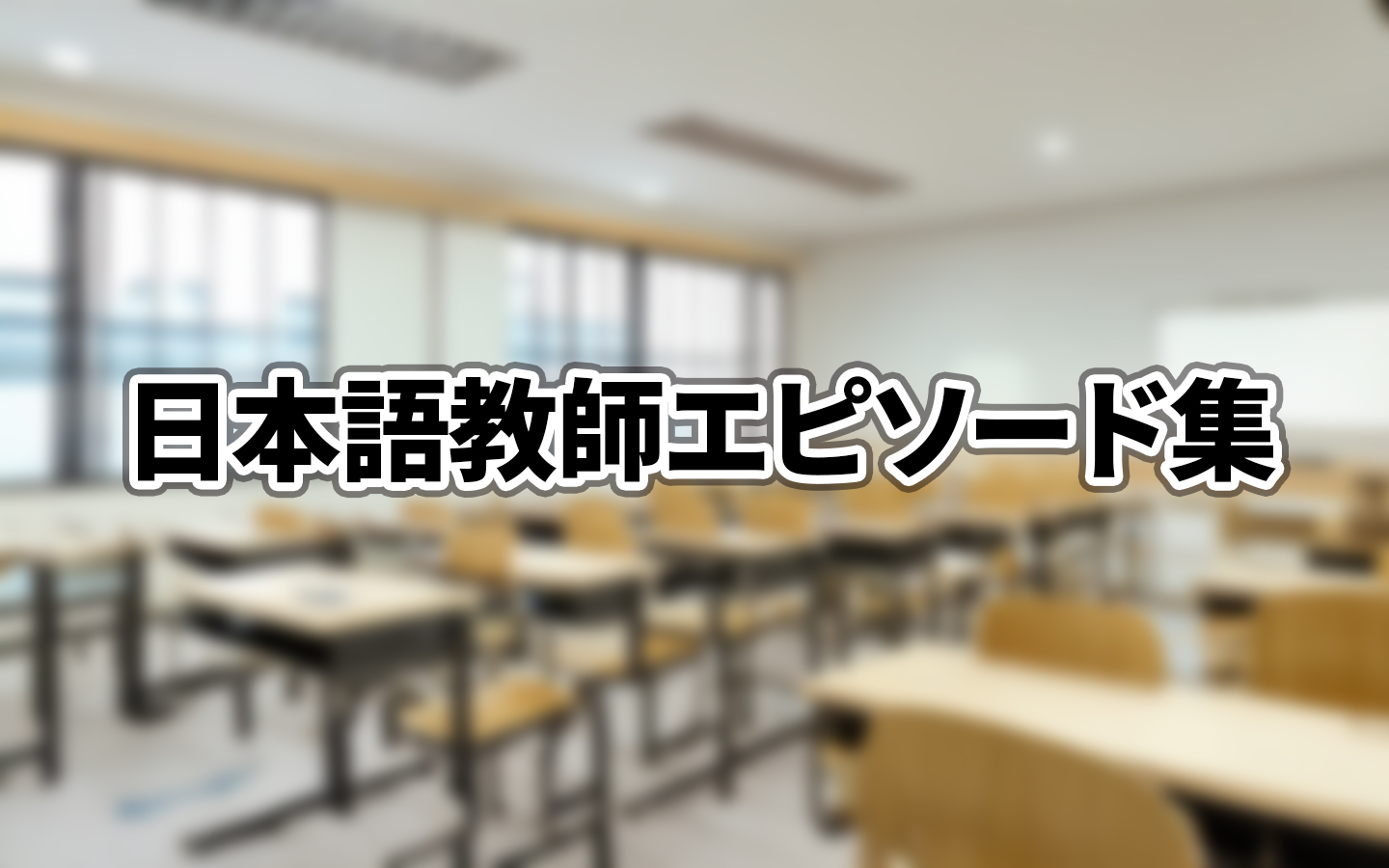

コメント