この記事は、日本語教師という仕事が実は日本語教育に関わりがない人々にとっては実は全く知られていないのではないかという感覚に基づいて、あるあるエピソードを交えて記述しています。
一言で言うと
「日本語教師やってるの?英語話せるの?」や、「日本語教えるなんて、日本人なら誰でもできるじゃん」は何回も擦(こす)られてきた「日本語教師あるある」であるが、ではどう説明するかについてはきちんと言語化しておかないと、なかなか世間一般には伝わらないという話。
そもそも「日本語学校」であって、「日本人学校」ではない
スタートはここからです。世間の方々は、「日本語学校」も「日本人学校」も区別しないで生きておられる方がいます。仕方ありません。自分に関係のないことは覚えないのです。ですから、学生に語彙導入をするように、日本語学校とは、留学生が日本で進学や就職を目指して、日本語を日本語で勉強するところだよ、と説明してあげる必要があります。
日本語を日本語で勉強するということがまさに「直接法」の教授をしているということです。日本語を外国人に教えているすなわち英語で教えていると受け止める方は、外国人は英語を話すものという思い込みがあります。しかし、ざっくりと日本にいる外国人で英語話者は3割とか言われていて、英語が全てではないことは間違いありません。
だからこそ、街の「言語景観」は、英語だけでなく、中国語、韓国語、ベトナム語の併記になっています。このままあらゆる言語を併記することはスペース的に無理なので、「やさしい日本語」のように日本語をわかりやすいものに変えていこうという考え方もあります。
現在の日本における日本語学校の主流は、日本語を日本語で教えるという「直接法」と言っていいのでしょうか。私の友人は、「日本語だけでどうやって教えるの?」と目を丸くして言います。だから、日本語教師という職業があるんだよと説明するんですね。向こうの腑に落ちるまで、しばらく時間がかかるのは言うまでもありません。
日本語を何語で教えるかという話の前に、日本人学校と勘違いされると、教育の目的や内容が全く違うものになります。明らかに別物じゃないかというツッコミ、私もそう思うのですが、つい勘違いしたまま話が続くことがありますので、ちゃんと伝わっているかを確認しながら話を続けなければなりません。
日本語教師といってもいろいろな件
ひとことに日本語教師といっても、範囲が広いです。日本語学校、大学院、大学、短大、専門学校、日本語教室、オンライン教師、企業での日本語教育担当者、その他さまざまな形で日本語を教えることを仕事にしている方がいらっしゃるでしょう。
「私たち日本語教師が」という主語をつくるときは気をつけなければなりません。私の立場からすると、法務省告示校である日本語学校という定義になります。大学などの上級学校については経験がないので、詳しく知りません。
逆に、日本語を教えているという意味では、先生であるかどうかにかかわらず、コンビニの店長さんが留学生アルバイトに仕事のための日本語を教えれば、役割としては先生です。日本語学校で学習したことだけで留学生は日本語を習得していくのではなく、アルバイトや社会でのやりとりの中で、日本語を習得していきます。こういう意味で「日本語の先生」はあちこちにいるのです。
数が少ないので、世間は狭い
日本語学校があまたあるとはいえども、すべての都道府県にすきまなく存在しているわけではありません。日本に来たい外国人にとって、やはり人気がある都市は、東京、大阪の順だそうです。私は大阪府にいますので、比較的多い方だとは思うのですが、他の県などをみると、案外少ないんだなというのが率直な感想です。
日本語学校(告示校)の特色
これって私の感想なんのですが、日本語学校(告示校)の一番の特色は、留学生の入口、まさに玄関にあたるということです。専門学校や大学に進学する際には、専門的な勉強ができるように、それなりに学習が進んでいることが建前です。
もちろん、留学生として日本語学校に入学するすなわち、「留学ビザ」を取得するためには、基礎的な日本語(JLPT、日本語能力試験N5相当)でなければならないことになっています。基本的なコミュニケーションができるはず、ですが、実際に日本語学校に入学すると、ひらがな・カタカナやばない?というケースが山程あります。
0を1にするのが日本語学校だ、と私は割り切っています。国であるていど勉強してくるのが建前ですが、現場はそうはいきません。1年生でも、2年生でも、つねにスタート地点からみて、0を1に引き上げて、あとは自律的な学習サイクルを身に着けさせて、上級学校を目指してもらうのが日本語学校の役割、と考えているんですね。現実にはいろいろ「使命」があるようですが。
中学校の先生に「小学校でならわなかったの?」とか、高校の先生に「中学校でならわなかったの?」とか、学校の先生って、かならず前の学校でどうだったか言ってくるよな、と生徒・学生だった頃の私は思いました。それは段階的に、連続した教育政策、プログラムの中で分担され、積み上げられているこものなので、先生からすればこういうものの言い方になるのも仕方ありません。
日本語学校というところは、もう日本にきてしまった以上は、とにかく少しでも前に進めて、次のステップに送り出さなければいけないところです。政策的にざっくりとやって、80%進学したね、よかったねと言ってられません。最後の1人までなんとかしなければ、その学生は大変なことになってしまいます。
日本語を教えるという仕事については他の日本語教育機関と共通ではありながら、日本語学校はもう少し学生個人の人生に密着した局面が多い仕事だと思います。異文化の境目、玄関ですから、さまざまな問題も起こります。学生もトラブルや危機に見舞われます。
そうした生々しいところまで含めて、学生と向き合っていくのが楽しいと思えれば、日本語学校の仕事は実に楽しくやり甲斐があります。しかし、日本語を教えることに集中したいという思いが強いと、日本語教師の各局面で悩むことも多くなるでしょう。
まとめ
働き手不足の日本に、外国人がこれからもたくさんやってくることは止められない流れです。実質的な「移民」の是非についての議論もありますが、来ちゃったからには、日本語をしっかり習得してもらって、社会に参加して馴染んでいってもらいたいというのが、私の個人的な考えです。
目の前の学生を、今日よりも明日もうひとつと、日本語でコミュニケーションによって「できることを増やす」のが日本語教師の仕事です、と私は答えます。
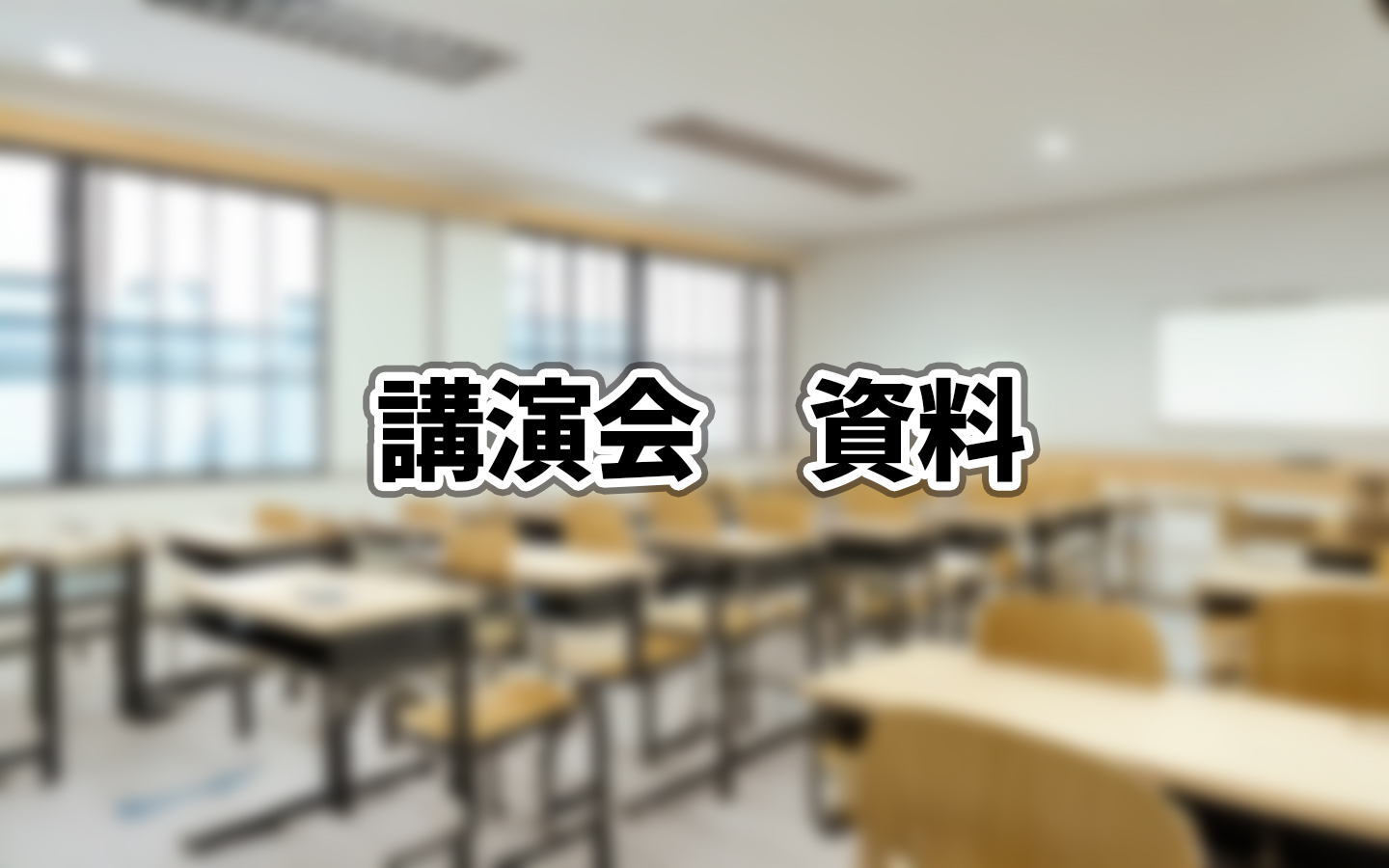

コメント